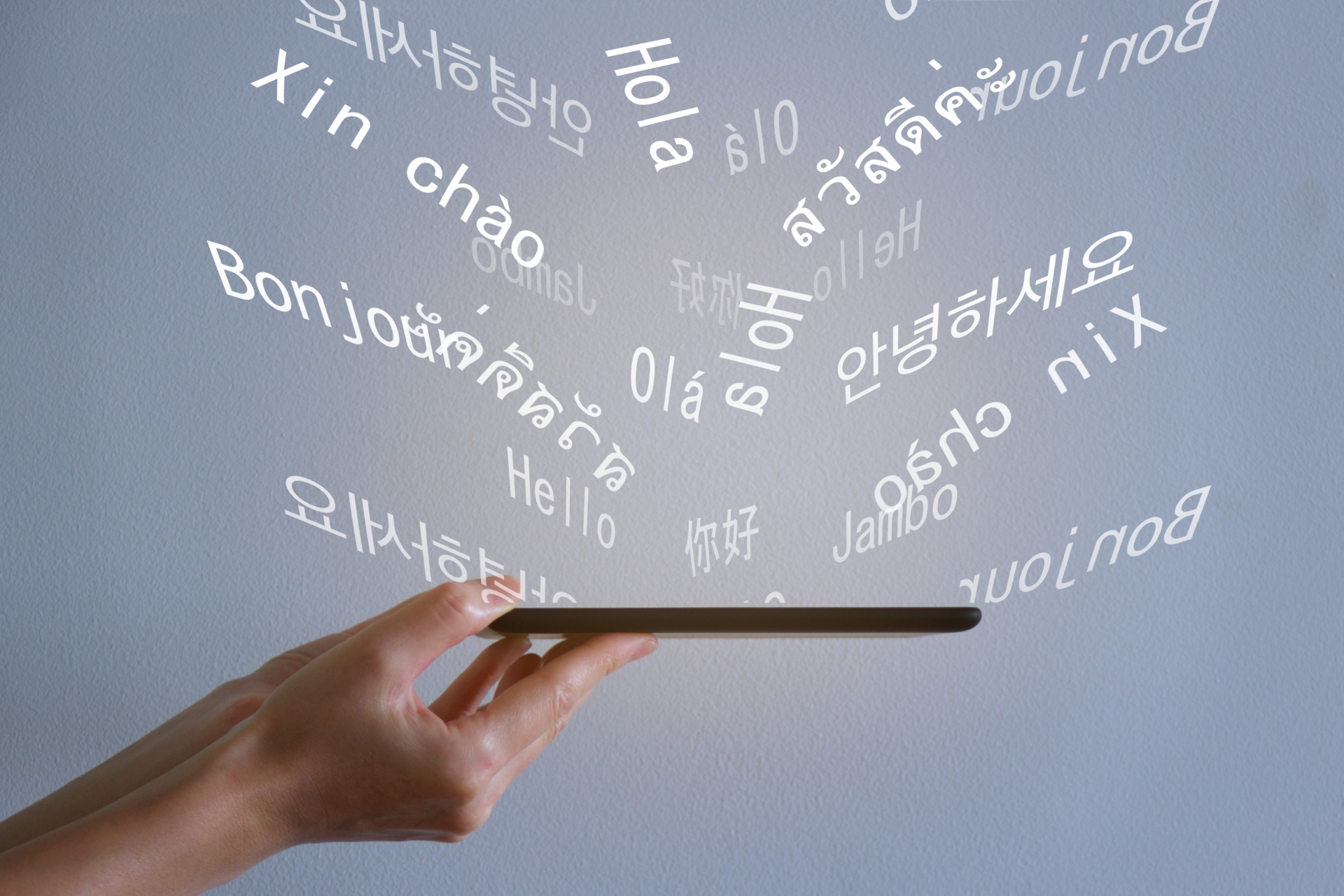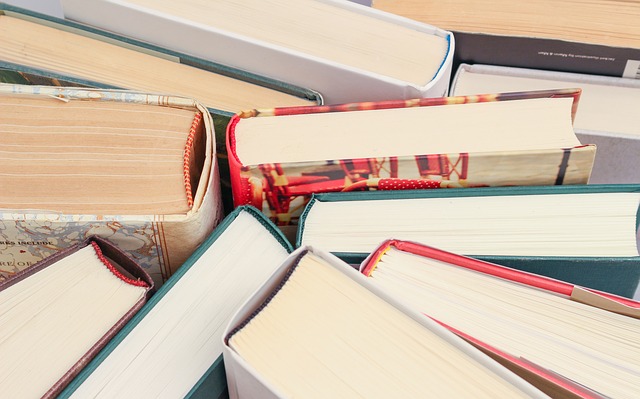2024年6月14日
機械翻訳の精度を上げるには?賢く英訳する19のポイント
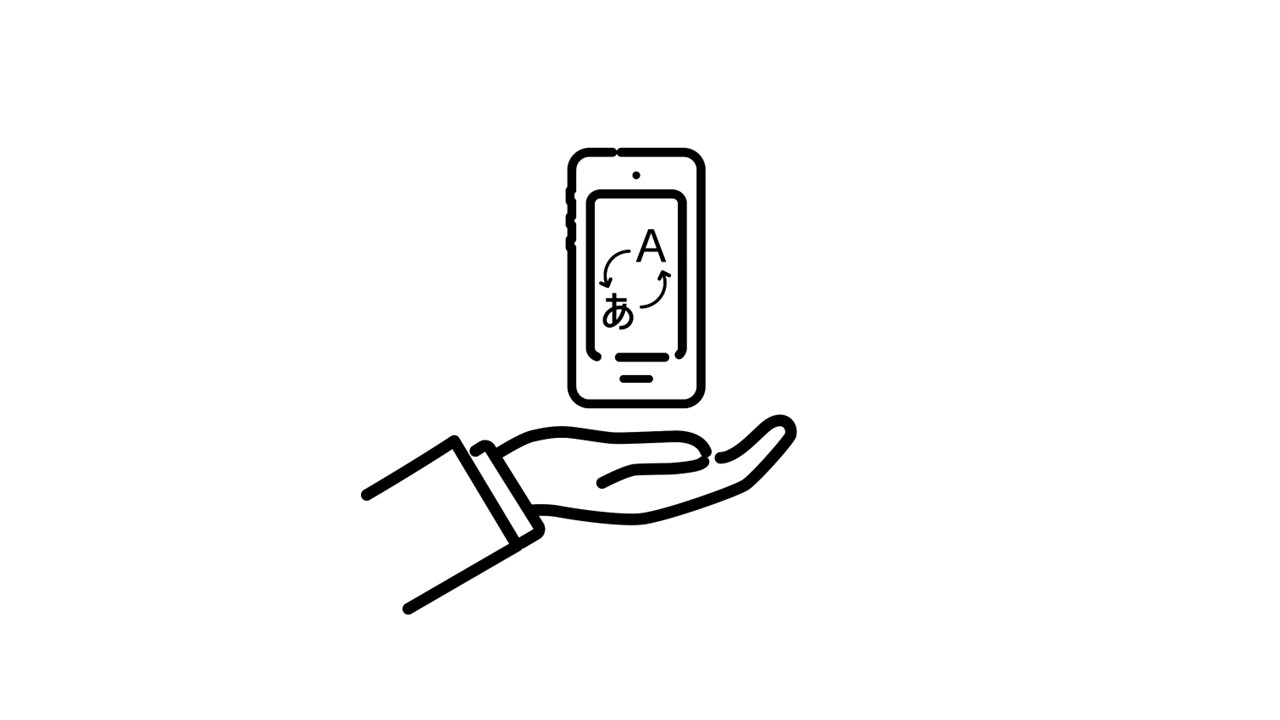
この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。
近年のグローバル化によって、多言語対応が求められる場面が増加し、翻訳サイトを利用する機会も増えているのではないでしょうか。
AI技術の進歩により、機械翻訳の精度は以前より向上していますが、それでも「不自然な文章になる」「正確に意図が伝わらない」といった課題は依然として見受けられます。
日常的な会話やカジュアルなやりとりであれば、多少の違和感があっても問題にならないことが多いでしょう。しかし、ビジネスの場面では、できる限り正確な翻訳が求められます。
翻訳会社への依頼や、ネイティブチェックを活用するのが理想ではありますが、機械翻訳を使用する場合でも、いくつかのポイントを押さえることで翻訳の質を大きく向上させることが可能です。
本記事では、機械翻訳をより効果的に使うための19のポイントをご紹介します。
▼マニュアルの翻訳については、以下の記事もあわせてご覧ください。
日本語の特徴と機械翻訳の特徴とは?
まずは、日本語と英語の構造の違い、そして人間の翻訳と機械翻訳の違いについて改めて確認しておきましょう。これらの特徴を理解しておくことで、機械翻訳をより効果的に活用することができます。
日本語と英語の主な違い
日本語と英語には主に以下のような違いがあります。機械翻訳の原文となる日本語を作成する際には、英語に合わせた表現を意識することが重要です。
| 日本語 | 英語 |
| 曖昧な表現が多く、断定を避ける | 直接的で断定的な表現が多い |
| 主語や目的語を省略しやすい | 省略が少ない |
| 語順:S(主語)+O(目的語)+V(動詞) | 語順:S(主語)+V(動詞)+O(目的語) |
| 文が長くなりやすい | 短く簡潔な文が多い |
| 無生物が主語になりにくい | 無生物も主語になり得る |
| 結論を最後に述べる | 結論を先に述べることが多い |
人間による翻訳と機械翻訳の違い
人間による翻訳と機械翻訳のもっとも大きな違いは、「書かれていない部分を推測して補えるかどうか」です。機械翻訳では、基本的に原文に書かれていない内容を補完することができないため、省略部分を明確に補足しておく必要があります。
| 人間による翻訳 | 機械翻訳 |
| 行間を読み取れる | 行間を読み取れない |
| 文脈から不足部分を補える | 文脈から不足部分を補えない |
| 原文に誤字脱字があっても翻訳できる | 原文に誤字脱字があると誤訳の原因に |
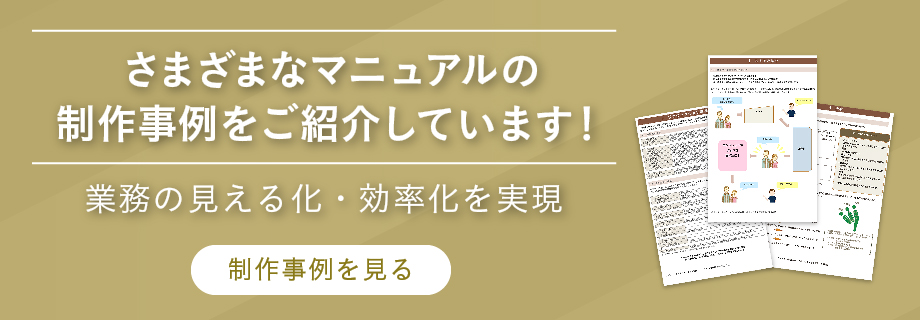
機械翻訳を使うときのポイント
1.長文を避け、なるべく一文を短く簡潔にする
機械翻訳を利用する際の基本的なポイントは、「文を短く切る」ことです。日本語では一文に複数の話題を盛り込むことができますが、一文が長くなると文の構造が複雑になり、誤訳を招きやすくなります。
「~ので」や「~だが」といった接続詞が多用されている場合は、文を分けて整理し、一文を短くすることを心がけましょう。
(例)大型台風の接近により、大気の状態が不安定であり、
各航空会社が今日の便の欠航を発表している。
↓
大型台風の接近により、大気の状態が不安定である。
そのため、各航空会社が今日の便の欠航を発表している。
2.省略された語句を補う
日本語では主語や目的語が省略されても意味が伝わることが多いですが、機械翻訳では省略部分を正確に補完することが難しく、正しい意味が伝わらないおそれがあります。
そのため、原文を作成する際には、主語や目的語といった省略しがちな部分を明確に記述することで、翻訳の精度を高めることができます。
(例)ご応募をお待ちしております。
↓
皆様のご応募をお待ちしております。
3.具体的な動詞を使う
「~になる」「~を行う」「~する」といった汎用的な動詞はさまざまな主語や目的語に対して使われますが、機械翻訳では正しく翻訳されないことがあります。
より具体的な動詞に言い換えできる場合は、限定的な意味の動詞を使うのがおすすめです。
(例)眼鏡をする。
↓
眼鏡をかける。
4.不要な言い回しや曖昧な表現を避ける
日本語では「~ということ」「~ものである」「~したいと思う」などの曖昧な言い回しがよく使われますが、機械翻訳ではこうした言い回しが誤訳の原因になることがあります。翻訳精度を高めるためには、簡潔かつ明確な表現を心がけましょう。
(例)焦っても良い結果は生まれないものである。
↓
焦っても良い結果は生まれない。
5.なるべく漢字に変換する
日本語は英語と異なり、単語の間にスペースがないため、ひらがなばかりの文章では単語の区切りを企画が正確に認識しづらくなります。漢字に変換できる部分は極力漢字に変換してから、機械翻訳を利用するようにしましょう。
(例)きょうとあしたいこうとおもいます。
↓
今日と(きょうと)明日行こうと思います。
京都(きょうと)明日行こうと思います。
また、同音異義語などによる変換ミスがある場合も、機械翻訳ではそのまま翻訳されてしまうことがあります。翻訳結果に違和感を覚えた際は、原文の漢字表記に誤りがないか確認してみてください。
(例) 意味慎重
meaning carefully
↓
意味深長
Meaningful
6.適切な助詞を使う
文中の「てにをは」などの助詞に気を付けるだけでも、翻訳の精度は大きく向上します。
特に、「ウサギは耳が長い」の「は」のように主格を表さない「は」や、「子供達の帰った後に」の「の」のように主格を表す「の」には注意が必要です。日本語としては意味が通っていても、英語では翻訳結果が異なる場合があります。
(例)この分野に関する特許は取得が難しい。
↓
この分野に関する特許の取得は難しい。
7.定着していない略語は使用しない
「エアコン」「パソコン」など一般的に認知された略語は問題ありませんが、あまり知られていない略語は、機械翻訳では正しく理解されないことがあります。
専門用語も同様に、機械翻訳では意味が正しく伝わらない場合があるため、できる限りわかりやすい語に言い換えることをおすすめします。頻出専門用語や固有名詞は、ユーザー辞書に登録しておくのもよいでしょう。
(例)タイパ
Taipa
↓
タイムパフォーマンス
time performance
8.係り受けを明確にする
「主語と述語」「修飾語と被修飾語」など、語句同士の関係をはっきりさせることが重要です。
人間であれば文脈から意味を読み取ることができますが、機械翻訳では複雑な文脈構造を正しく解釈できない場合があります。語順を見直すなどして、誰が読んでも明確に解釈できる文章に整えましょう。
(例)彼は新発売のお菓子と弁当を買った。
↓
彼は弁当と新発売のお菓子を買った。
9.重複表現を避ける
こちらは機械翻訳に限ったことではありませんが、内容が重複していると意味がわかりにくくなり、誤訳の原因にもなってしまいます。無駄のない簡潔な表現を心がけましょう。
(例)記入の際には注意事項をよく読んでから記入してください。
↓
注意事項をよく読んでから記入してください。
10.慣用句や比喩表現は避ける
ことわざ、四字熟語、比喩など、日本語特有の慣用表現は、機械翻訳では意味が伝わりにくく、誤訳の原因になります。例えば、「鼻が高い」という表現は、Google翻訳では「high nose」と訳されてしまい、本来の意味が伝わりません。こうした表現は、意味が伝わる平易な表現に言い換えるようにしましょう。
(例)私にとっては朝飯前だ。
It’s just breakfast for me.
↓
私にとっては簡単だ。
It’s easy for me.
11.複雑な複合語は避ける
「海風」「考え事」など、二つ以上の単語が組み合わさった名詞を複合名詞、「走り回る」「近寄る」など、二つ以上の単語が組み合わさった動詞を複合動詞と言います。
上記のような単純な複合語であれば問題ありませんが、単語が多数組み合わさった複合語の場合、機械翻訳では単語の塊を正確に読み取ることが難しく、誤訳の原因になることがあります。可能な限り、文を分割したり、より単純な表現に言い換えるようにしましょう。
(例)発車時前方安全確認
↓
発車時に前方の安全を確認する
12.造語を避ける
日本語では「~的」「~性」「~化」などを使った造語が多用されますが、機械翻訳ではこれらのニュアンスを正しく捉えることが難しい場合があります。あいまいな造語の使用は避け、意味が明確に伝わる別の表現に置き換えることをおすすめします。
(例)コストパフォーマンス性に優れたパソコン
Cost performance of the excellent personal computer
↓
優れたコストパフォーマンスのパソコン
Excellent cost performance of the personal computer
13.無生物主語を使う
英語には無生物が主語になる表現があります。以下の例のような無生物が主語の場合は、それを意識した書き方をすることで、機械翻訳でも自然な表現に翻訳されやすくなります。
(例)マニュアルによって業務が効率化した。
↓
マニュアルが業務の効率を上げた。
14.擬音語・擬態語の使用は避ける
「しとしと」「わくわく」といった擬音語・擬態語は、日本語と英語で表現が異なる場合が多く、機械翻訳ではニュアンスが正確に伝わらないことがよくあります。翻訳精度を高めるためには、こうした擬音語・擬態語の使用は避け、より具体的な描写に置き換えるようにしましょう。
(例)犬がワンと吠える
↓
犬が吠える
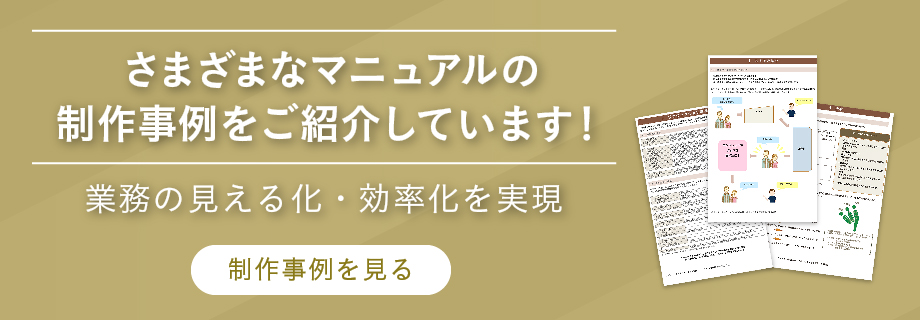
英訳後に編集するときのポイント
日本語に存在しない「単数・複数」「冠詞」などの文法要素は、英訳後に必要に応じて編集が必要です。ここからは、英訳後のチェックポイントをご紹介します。
1.単数・複数の確認
「多くの」「三人の」など、原文に複数を示す情報が含まれていれば、英文でも複数形が使われることが一般的です。しかし、そうした手がかりがない場合は、単数・複数が適切に訳されないことがあります。
翻訳後は、名刺の単数形・複数形が適切に反映されているかを確認しましょう。
(例)
原文:教授が学生に対して哲学を講義している。
訳文:Professor is lecturing the philosophy to a student.
編集後:Professor is lecturing the philosophy to students.
2.冠詞の確認
英語では「a」「an」「the」などの冠詞によって、名詞が特定のものかどうかを明示します。一方、日本語には冠詞の概念がないため、翻訳後は文脈に応じて適切な冠詞がついているかを確認し、必要に応じて修正することが大切です。
(例)
原文:領収書を受け取った。
訳文:I received a receipt.
編集後:I received the receipt.
3.時制の確認
日本語では、仮定法や現在完了、過去完了といった細かな時制の違いが曖昧なことがあります。そのため、翻訳後に文脈にあった時制が正しく使われているかをチェックしましょう。
(例)
原文:子供だったころから私は彼のことを知っている。
訳文:I know him since I was a child.
編集後:I knew him since I was a child.
4.代名詞の確認
日本語では主語や目的語が省略されることが多く、「this」「it」「he」「you」といった代名詞も明示されないことがあります。英語ではこれらの代名詞を省略せずに表現する必要があるため、翻訳後に文脈に合った代名詞が使われているか確認しましょう。
(例)
原文:回答ありがとうございます。
訳文:Thank you for an answer.
編集後:Thank you for your answer.
5.前置詞の確認
「at」「to」「for」「from」などの前置詞は、単語や文脈によって適切なものが異なります。機械翻訳では文脈に合わない前置詞が使われている場合もあるため、翻訳後に確認が必要です。
(例)
原文:この机は木から作られている。
訳文:This desk is made from wood.
編集後:This desk is made of wood.
まとめ
今回は、機械翻訳を上手に活用するためのポイントをご紹介しました。
高い精度や完璧な表現を求める場合は、翻訳会社への依頼やネイティブによるチェックが理想的です。しかし、機械翻訳を活用しつつ、足りない部分を人の手で補うことも、効率を品質を両立させるための一つの方法です。
日本語と英語では文の構造や表現方法が大きく異なるため、機械翻訳だけで完璧な翻訳を行うのは難しい場面もありますが、ちょっとしたポイントを押さえるだけでも、翻訳の精度を大きく向上させることができます。
ぜひ今回のポイントを参考に、機械翻訳を上手に取り入れてみてください。