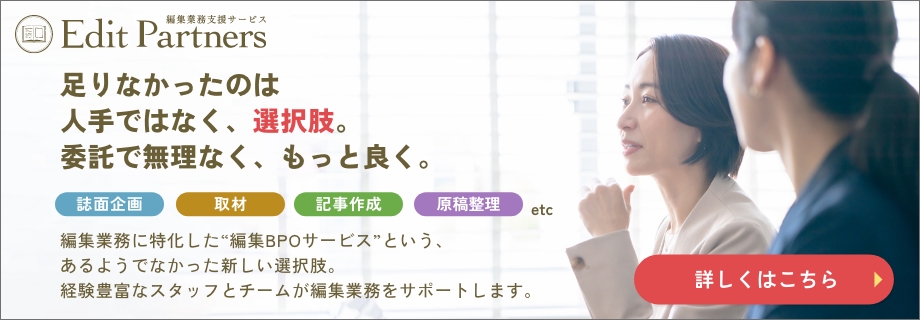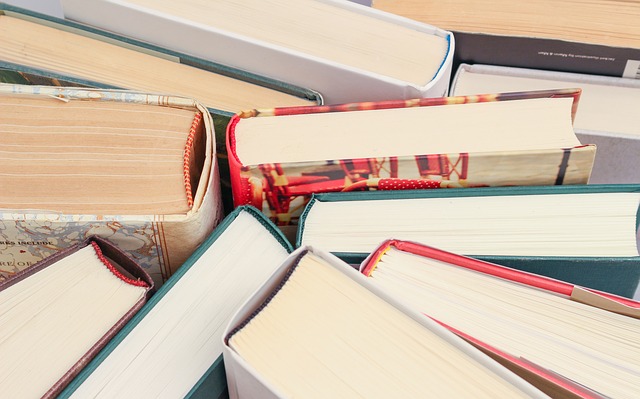2025年6月13日
間違えやすい慣用句56選! 正しい意味と使い方、読み方を解説

この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。
日常会話や文章の中で、何気なく使っている慣用句や言い回し。実は、意味や用法を間違えて使ってしまっているケースも少なくありません。間違ったまま使い続けると、ビジネスシーンやフォーマルな場面で誤解を招いたり、相手にマイナスな印象を与えてしまう可能性もあります。
この記事では、誤用されやすい慣用句や語句、ことわざについて、正しい意味と使い方を解説します。
▼以下の記事では、文章における漢字とひらがなの使い分けについてご紹介しています。あわせてご覧ください。
慣用句とは?
慣用句とは、複数の言葉が組み合わさって、一定の意味を持つ決まった表現のことを指します。文字どおりの意味ではなく、比喩的なニュアンスを含んでいるのが特徴です。
例えば、「顔が広い」という表現は、実際に顔の大きさを指すのではなく、「知り合いが多い」「交友関係が広い」といった意味で使われます。このように、慣用句は文脈の中で特定の意味を持つ表現として定着しています。
よく慣用句と混同されやすいのが「ことわざ」です。ことわざと慣用句の大きな違いは、教訓や人生の知恵が含まれているかどうかという点です。ことわざは、古くから言い伝えられてきた教訓や知恵を短い言葉で表したもので、「石の上にも三年」や「急がば回れ」などが例として挙げられます。
まとめると、慣用句は比喩的な言い回しとして定着した表現であり、ことわざは教訓や普遍的な真理を伝える短文であるという点が、それぞれの大きな違いです。
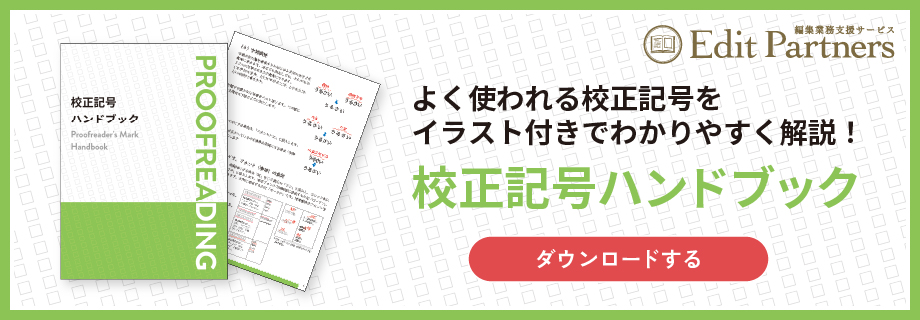
間違えやすい慣用句
1.てにをはの間違い
| ×誤 | ○正 | 意味・解説 |
|---|---|---|
| 手が負えない | 手に負えない | 自分の力では扱いきれないこと |
| 恩を着せる | 恩に着せる | 恩を施したことに対して、ありがたく思わせようとすること |
| 上や下への大騒ぎ | 上を下への大騒ぎ | 秩序が乱れ、混乱している様子 |
| 藁にもつかむ | 藁をもつかむ | 差し迫った状況で、普段なら頼りにしないようなものにすら助けを求めること。 「藁にもすがる思いで」とは言いますが、「藁にもつかむ」とは言いません。 |
| 濡れ手に粟 | 濡れ手で粟 | 濡れた手で粟をつかむように、苦労することなく大きな利益を得ること。 |
2.漢字の間違い
| ×誤 | ○正 | 意味・解説 |
|---|---|---|
| 過去の誤ち | 過去の過ち | 過去に犯したミスや間違いのこと |
| 凌ぎを削る | 鎬を削る | 刀の鎬を削り落とすほど、互いに激しく争い合うこと |
| 袖振り合うも多少の縁 | 袖振り合うも多生の縁 | たとえ道ですれ違って袖が触れ合うだけのような偶然も、 前世からの深い因縁によるものであるということ |
| 一同に会する | 一堂に会する | 多くの人が一か所に集まること。「一堂」は場所を指す言葉で、 「一同(人々)」と混同しないように注意しましょう。 |
3.動詞の間違い
| ×誤 | ○正 | 意味・解説 |
|---|---|---|
| 上には上がいる | 上には上がある | どんなに優れていると思っても、それ以上の存在は必ずあるということ。 人に限らず物事に対しても使えるため、「ある」が正しい表現です。 |
| 顰蹙を買われる | 顰蹙を買う | 言動が原因で人に不快感を与え、嫌われたり批判されたりすること。 「顰蹙(ひんしゅく)」とは、顔をしかめたり眉をひそめるなどして 不快感を表すしぐさを指します。 |
| 合いの手を打つ | 合いの手を入れる | 相手の話や歌にタイミングを合わせて、掛け声などを入れること。 もともとは歌の合間に楽器演奏を入れることを意味していました。 |
| 脚光を集める | 脚光を浴びる | 舞台でスポットライトを浴びるように、世間から注目されること。 「注目を集める」と混用しやすい表現です。 |
| 熱にうなされる | 熱に浮かされる | 高熱で意識がもうろうとしたり、何かに夢中になって冷静さを失ったりすること。 高熱が出てうなされることはあるかもしれませんが、「熱にうなされる」は誤用です。 |
| 采配を振るう | 采配を振る | 先頭に立って指示・指揮すること。 |
| 物議を呼ぶ | 物議を醸す | 世間に議論や論争を巻き起こすこと。 「議論を呼ぶ」と混同しやすい表現です。 |
| 雪辱を晴らす | 雪辱を果たす | 過去に敗れた相手に勝ち、恥をそそぐこと。 「雪辱」は「恥をすすぐ」という意味を含んでいるため、 「雪辱を晴らす」だと意味が重複してしまいます。 |
| のべつくまなし | のべつまくなし | 絶え間なく、ひっきりなしに続く様子。 「のべつ」は休みなくずっと、 「幕なし」は芝居で幕を引かずに演じ続けることを意味します。 |
| 眉をしかめる | 眉をひそめる | 心配や不快な思いをしたときに、眉間にしわを寄せること。 「顔をしかめる」と混用しやすい表現です。 |
| 押しも押されぬ | 押しも押されもせぬ | 押しも押されもしない、実力があり堂々と認められている様子。 |
| 声をあらげる | 声をあららげる | 感情が高ぶって大声や荒い口調で話すこと。 |
| しかめつらしい | しかつめらしい | まじめすぎて堅苦しい様子。 「しかめっ面」との混同から誤用されることが多いです。 |
| 怒り心頭に達する | 怒り心頭に発する | 強い憤りを感じ、激しく怒ること。 「心頭」とは心の奥底を指し、 心の底から怒りがこみあげてくることを表しています。 |
4.名詞の間違い
| ×誤 | ○正 | 意味・解説 |
|---|---|---|
| 顔の皮が厚い | 面の皮が厚い | 恥知らずでずうずうしいこと。 |
| 印籠を渡す | 引導を渡す | 相手に諦めさせるための最終戦国をすること。 もともとは、人を導いて仏道に入れること、 転じて、死んだ事を分からせる儀式を行うということです。 |
| 頭を傾げる | 首を傾げる | 何か不思議に思ったとき、疑問に思ったときの動作。 |
| 足元をすくわれる | 足をすくわれる | 隙をつかれて失敗に追い込まれること。 「足元を見る」との混同に注意が必要です。 |
| 目鼻が利く | 目端(めはし)が利く | 機転が効くこと。「目が利く」「鼻が利く」という表現はありますが、 目鼻が利くとは言いません。 |
| 愛想を振りまく | 愛嬌を振りまく | 周囲に好かれるような、にこやかで親しみやすい態度をとること。 |
| 口車を合わせる | 口裏を合わせる | あらかじめ話の内容を相談しておき、食い違いがないようにすること。 「口車」は「乗る・乗せる」と表現します。 |
| 寄る年には勝てぬ | 寄る年波には勝てぬ | どんなに努力しても、加齢による衰えには逆らえないこと。 「年が寄る」と「波が寄る」をかけた表現です。 |
意味を間違えやすい慣用句・ことわざ・語句
| 意味・解説 | |
|---|---|
| 煮詰まる | 「議論が行き詰まってしまい結論が出ない状態」として使われがちですが、 本来は「議論や意見が十分に出尽くして結論に近づくこと」を指します。 |
| さわり | 出だしや最初の部分の意味と解釈されることが多いですが、 本来は話の要点や見せ場のことを指します。 |
| 敷居が高い | 不義理をしたことから、その人に会いに行くのに気が引けること。 近年では、高級すぎて手が出しにくい、ハードルが高いという誤った意味での使用が増えています。 |
| 姑息 | 「卑怯」「ずる賢い」という意味で使われることが多いですが、正しくは「その場しのぎ」という意味です。 |
| 破天荒 | 豪快で大胆な人を表す言葉として使われることが多いですが、 正しくは「これまで誰も成し遂げなかったことを初めて成し遂げること」です。 |
| 失笑 | 堪えきれずに笑ってしまうこと。 冷笑したり、笑いがとれないことではありません。 |
| なしくずし | 物事を曖昧にすることではなく、正しくは「物事を少しずつ進めること」です。 漢字では「済し崩し」と書き、借金を少しずつ返済することが本来の意味です。 |
| 役不足 | 与えられた役割がその人の実力よりも軽いこと。 「荷が重い」「大役すぎる」という意味の「力不足」と混用して使われることが多いです。 |
| 潮時 | 物事を行うのに適した時期のこと。潮の満ち引きを見て漁に出る時間を判断していたことが由来で、 「やめどき」といったネガティブな意味ではありません。 |
| 割愛する | 「不要なものを省略すること」ではなく、 正しくは「惜しいと思うものを手放すこと」を指します。 |
| 気が置けない人 | 正しくは「遠慮や気兼ねの要らない人」のことです。 油断できない人や気が許せない人という意味で誤用されやすいですが、 本来は正反対の意味です。 |
| 情けは人のためならず | 「人に情けをかけて助けても、結局その人のためにならない」ということではなく、 正しくは「人に情けをかけることは、巡り巡って自分のためになる」という意味です |
| 檄(げき)を飛ばす | 「元気がない人に対して激励したり、元気づけること」ではありません。 正しくは、「自分の意見や考えを、広く人に知らせて同意を求めること」という意味です。 |
| 雨模様 | 本来は「今にも雨が降りそうな状態」(まだ降っていない状態)を指す言葉です。 ただし、最近では「雨が降っている状態」や「降ったり止んだりしている状態」の意味で 使われることも多くなっており、この用法を認める辞書もあります。 |
| 確信犯 | 本来は、宗教・政治・思想上の信念に基づき、本人が正しいと信じて行う犯罪や、そのような行為をする人を指します。 近年では、「悪いこととわかっていながら行われた犯罪や行為」 また「それを行った人」を指す意味でも使われるようになっています。 |
| 他山の石 | もともと「他の山から出た粗末な石」という意味から転じて、他人のつまらない言動であっても、 自分の知恵や人徳を高めるための参考にするという意味の表現です。 他人の立派な言動を手本にするという意味ではありません。 |
| 鳥肌が立つ | 本来は、恐怖や寒さによって皮膚がざらつく状態を指す表現です。 近年では「感動して鳥肌が立つ」といった使い方も見られ、 その用法を認めている辞書もあります。 |
読み方を間違えやすい慣用句・語句
| ×誤 | ○正 | 意味・解説 | |
|---|---|---|---|
| 一世一代 | いっせいいちだい | いっせいちだい | 一生に一度だけあること |
| 上意下達 | じょういげたつ | じょういかたつ | 「上意」は上の者の意思や命令、 「下達」(かたつ)は下に伝えて 意思疎通をはかることを言います。 |
| 素読 | すどく | そどく | 内容は考えずに、ただ文字を音読すること。 |
| 十指に余る | じゅっしにあまる | じっしにあまる | 10本の指で数えきれないほどたくさんあること。 「十進法」「十戒」「十傑」「十返舎一九」などは、 「じゅっ」ではなく「じっ」と読みます。 |
| 舌鼓を打つ | したづつみ | したつづみ | おいしいものを食べて満足すること。 「鼓」は「つづみ」と読み、打楽器の一種です。 |
| 斜に構える | はすにかまえる | しゃにかまえる | 物事に対して正面からではなく、皮肉な態度で臨むこと。 |
| あり得る | ありえる | ありうる | 可能性があること。「得る」は通常「える」と読みますが、 この表現では文語の「ありう」の連体形が 終止形として使われて残っているため、「ありうる」と読みます。 |
まとめ
今回は、間違えやすい慣用句や言い回しをご紹介しました。日本語には多くの表現があり、知らず知らずのうちに誤った使い方をしていた言葉もあったのではないでしょうか?
誤用の原因としては、間違えて覚えていたり、似た表現と混同していたりすることがよくあります。会話の中では気にならない場合でも、文章として残ることで読み手に誤解を与えたり、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。
日頃から言葉の意味を正しく理解し、適切な場面で使用できるように意識することが重要です。文章を作成する際には、少しでも意味や用法に不安を感じた表現があれば、一度立ち止まって調べてみるようにしましょう。
とはいえ、言葉は時代とともに変化していくものでもあります。もともとの意味とは異なる使い方が広まり、やがて辞書に記載されるなど、かつては誤用とされていた表現が一般的な用法として認められるケースも少なくありません。そうした言葉の変化にも目を向けつつ、まずは基本的な使い方をしっかりと押さえておくことが大切です。