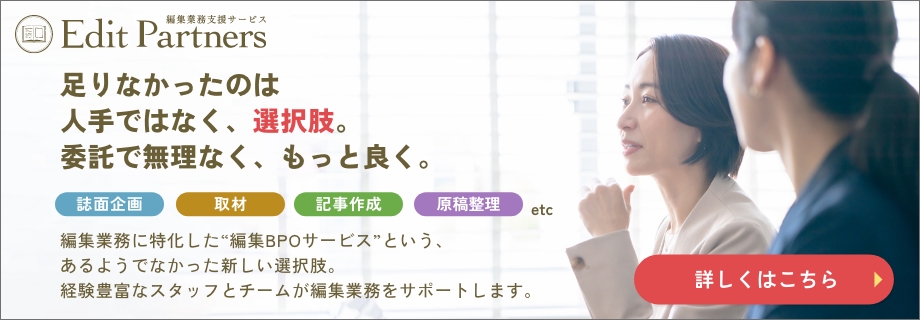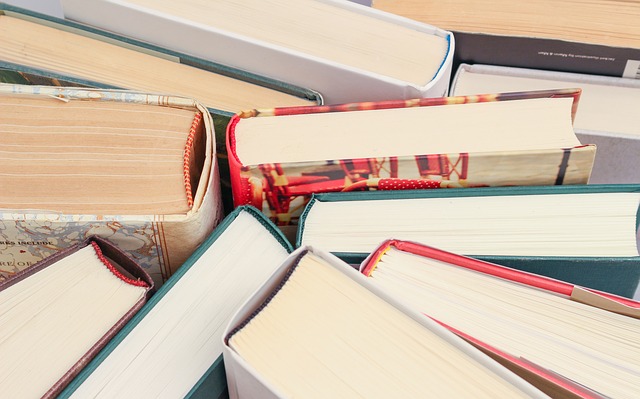2025年6月19日
【初めての社内報制作ガイド】 基本の流れを8ステップでわかりやすく解説

目次 ▼
この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。
社内報は、社員同士のコミュニケーションを促進し、会社の方針や取り組みを社内に浸透させるための有効なツールです。
とはいえ、「いざ担当になったけれど、何から始めればよいのかわからない」と戸惑う方も多いのではないでしょうか?社内報の制作には複数の工程があり、社内外の関係者との連携も欠かせないため、事前の計画と役割分担が非常に重要です。
特に、初めて担当する場合や、リニューアルを検討している場合は、制作全体の流れを把握しておくことで、スムーズに進行しやすくなります。
本記事では、社内報を制作するメリットと、制作に必要な8つのステップについてご紹介します。

社内報を制作する目的とメリット
社内情報の共有
社内報は、他部署の取り組みや成果、新制度の導入情報、社内イベントの案内など、社内のさまざまな情報を社員全体に届けるための手段です。
普段は部署や拠点ごとに分散している情報を集約し、全社員にスムーズかつ均等に共有することができます。
企業理念やビジョンの浸透
経営者からのメッセージや企業理念、ビジョンを社内報で発信することで、企業の価値観を社員に共有することができます。社員にとって目指すべき方向が明確になるとともに、組織としての一体感も醸成されます。
さらに、社内報を通じて「自社らしさ」を伝えることで、企業文化や風土の形成・定着にもつながります。
社員間のコミュニケーション促進
同じ会社にいても、他部署の状況や業務内容を知る機会は限られてしまいます。社内報は、部署間の情報交換や社員同士の相互理解を深めるきっかけとして有効です。
社員紹介や座談会、インタビュー記事などを通じて、他部門の雰囲気や業務内容が伝わりやすくなり、社内のつながりが生まれやすくなります。結果として、業務の円滑化や組織全体の活性化も期待できるでしょう。
社員のモチベーション向上
活躍している社員の紹介や表彰、成果などを取り上げることで、本人はもちろん、読者にとってもよい刺激となり、モチベーションの向上につながります。
「評価されている」と実感できる場があることは、働くうえでの大きな励みとなるでしょう。
制作前に決めておきたいこと
発行の目的
まずは「何のために社内報を発行するのか」という目的を明確にしましょう。先述のとおり、社内報には情報共有、理念の浸透、モチベーション向上などさまざまな目的がありますが、軸となる目的によってコンテンツの方向性やトーンも変わってきます。
発行の目的をはっきりしていれば、誌面全体のコンセプトや記事内容も決めやすくなります。
発行媒体、形式
紙媒体、PDF、Web、Share Pointなど、社内報にはさまざまな発行形式があります。
読者となる社員の年齢層や勤務環境(現場勤務、リモートワークなど)も考慮しながら、読みやすく、届きやすい形式を選びましょう。紙とWebを併用するのも一つの方法です。
▼Share Pointについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。
制作体制
社内報を、誰がどのような体制で作るのかを明確にします。社内で編集チームを設けるのか、外部の制作会社に依頼するのか、原稿作成・校正・デザインなどの役割分担も事前に決めておくとスムーズです。
社内のリソースやスキルに応じて体制を整え、関係部門との連携体制も明確にしておきましょう。
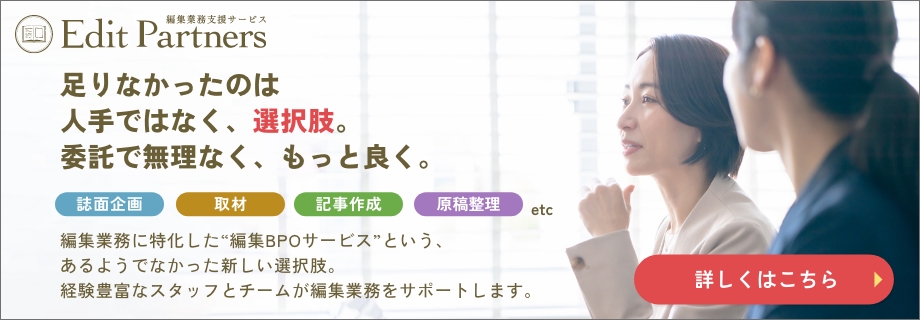
全体構成、仕様、ページ数
どんな内容を掲載するのか、記事のボリュームはどのくらいかといった、おおまかな誌面構成を考えます。
紙媒体の場合は、ページ数やサイズ、カラーかモノクロかといった仕様もあらかじめ決定しておく必要があります。
スケジュール
まずは年間スケジュールを確認し、発行頻度を検討しましょう(毎月・隔月・四半期・年1回など)。
発行頻度が決まったら、発行日から逆算して、企画立案・原稿作成・校正・修正・印刷・配信までのスケジュールを設計します。関係者が多い場合は、予想以上に時間がかかることもあるため、余裕を持った設計がポイントです。
▼進行管理には、年間計画表やガントチャートの活用もおすすめです。
・初心者にもおすすめ!使いやすいガントチャートツール6選
・無料で使える!年間スケジュール表のExcelテンプレート7選
デザインイメージ
外部の制作会社にデザインを依頼する場合は、事前にデザインイメージをしっかりとすり合わせておくと安心です。
誌面の雰囲気やトーン、色使い、フォントなど、できるだけ具体的なイメージを共有しましょう。過去の社内報や他社事例など、参考となるデザイン例を提示しておくと、完成イメージのズレを防ぎやすくなります。
社内報の目的やターゲット読者に合わせて、どのような印象を与えたいのかもあわせて伝えておくとよいでしょう。
社内報制作の流れ
1.企画を立てる
まずは、特集記事や連載など、掲載コンテンツの企画を考えます。編集会議でアイデアを出し合いながら、どんな情報を届けたいのか整理していきましょう。社員アンケートやヒアリングなどを活用して、読者のニーズを把握するのも有効です。
イベントや季節行事に合わせたタイムリーな企画も読者の関心を引きやすくおすすめです。
▼以下の記事では、社内報におすすめの企画・ネタをご紹介しています。
2.全体構成・レイアウトを設計する
企画内容が決まったら、各コンテンツの配置や全体構成を決めます。紙面サイズやページ数を考慮しながら、1ページあたりの情報量もバランスよく調整しましょう。ラフ案やワイヤーフレームを用意しておくと、後の工程もスムーズです。
また、構成が固まったら「台割」として一覧にまとめておくと、進行管理がしやすくなります。
▼台割の作り方は、以下の記事で詳しくご紹介しています。
3.取材・素材の収集
記事作成に必要な情報や素材を集めます。具体的には、社員インタビュー、写真撮影、イベント記録、データ収集などが挙げられます。
取材を行う際は、対象者の選定やスケジュール調整、撮影準備なども忘れずに行いましょう。
他の人に原稿の執筆を依頼をする場合は、文字数や締切、表記ルールなどの情報を共有しておくとスムーズです。
▼インタビュー取材の事前準備~当日の流れについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。
・成功の鍵!インタビューに必要な6つの事前準備とは?
・初めてでも安心!インタビューの進め方と失敗しない6つのポイント
4.原稿作成
取材内容や素材をもとに、記事原稿を作成します。読み手にとってわかりやすく、コーナーの趣旨に合ったトーンでまとめましょう。
外部ライターに依頼する場合は、必要な素材や参考情報を提供し、内容の正確さや読みやすさに配慮した執筆・編集を依頼しましょう。
▼以下の記事では、外部ライターに依頼する際のコツをご紹介しています。
5.デザイン・レイアウト
完成した原稿や写真などの素材をもとに、誌面のデザインとレイアウトを行います。
社内報の目的や企業のトーンに合わせて、可読性や視認性に配慮したデザインに仕上げることが大切です。文字サイズ、フォント、見出しの配置、画像のバランスなども、情報を効果的に伝えるためのポイントになります。
▼読みやすいレイアウトに関しては、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。
・文章の読みやすさを決める3つの要素、可読性・視認性・判読性とは?
・知らないとまずい!? 避けたほうがよい誌面レイアウトとは
6.校正・確認
デザインが仕上がったら、原稿内容とデザインが正しく反映されているかを確認します。内容に誤りがあると、読者の信頼を損なう原因にもなりかねません。誤字脱字、表記ゆれ、事実関係の誤りなどを丁寧にチェックしましょう。
複数人で確認することで精度は上がりますが、その分時間がかかることもあります。修正作業を見越して、余裕のあるスケジュールを組んでおくことが大切です。
▼校正の基本やコツは、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。
・今さら聞けない校正用語を解説!チェックすべき5つのポイントとは?
・誤字脱字を防ぐ9つのチェックポイントとは?原因と対策を解説
・表記ゆれを防ぐには?表記統一で気を付けたい9つのポイント
7.印刷・公開
校了後、紙媒体の場合は、印刷部数や納品スケジュールを確認したうえで印刷会社に依頼します。その後、印刷・製本を経て各拠点などに配布されます。
WebやPDF形式の場合は、社内ポータルやWeb、メール配信などを通じて公開します。
このとき、読者に確実に届けるための工夫も重要です。例えば、紙の場合は各部署にまとめて配布する、Webの場合はメールで更新を通知するなど、タイミングや導線にも配慮しましょう。
8.効果測定・振り返り
社内報は、発行して終わりではありません。発行後は読者の反応や閲覧数、アンケート結果などから効果測定を行い、改善点を洗い出しましょう。
「どのコンテンツが好評だったか」「伝わりにくかった点はどこか」などを分析し、次号に活かすことで、社内報の質がさらに高まります。
まとめ
今回は、社内報を制作するメリットと、制作の流れをご紹介しました。
社内報は、ただ情報を伝えるだけでなく、会社への理解や一体感を深めるための重要なコミュニケーションツールです。その効果を最大限に発揮するためには、企画や構成の段階でしっかりと設計し、計画的に制作を進めることが重要です。
ぜひ本記事でご紹介した8つのステップを参考に、自社に合った体制とスケジュールを整えて、社内報づくりに取り組んでみてください。