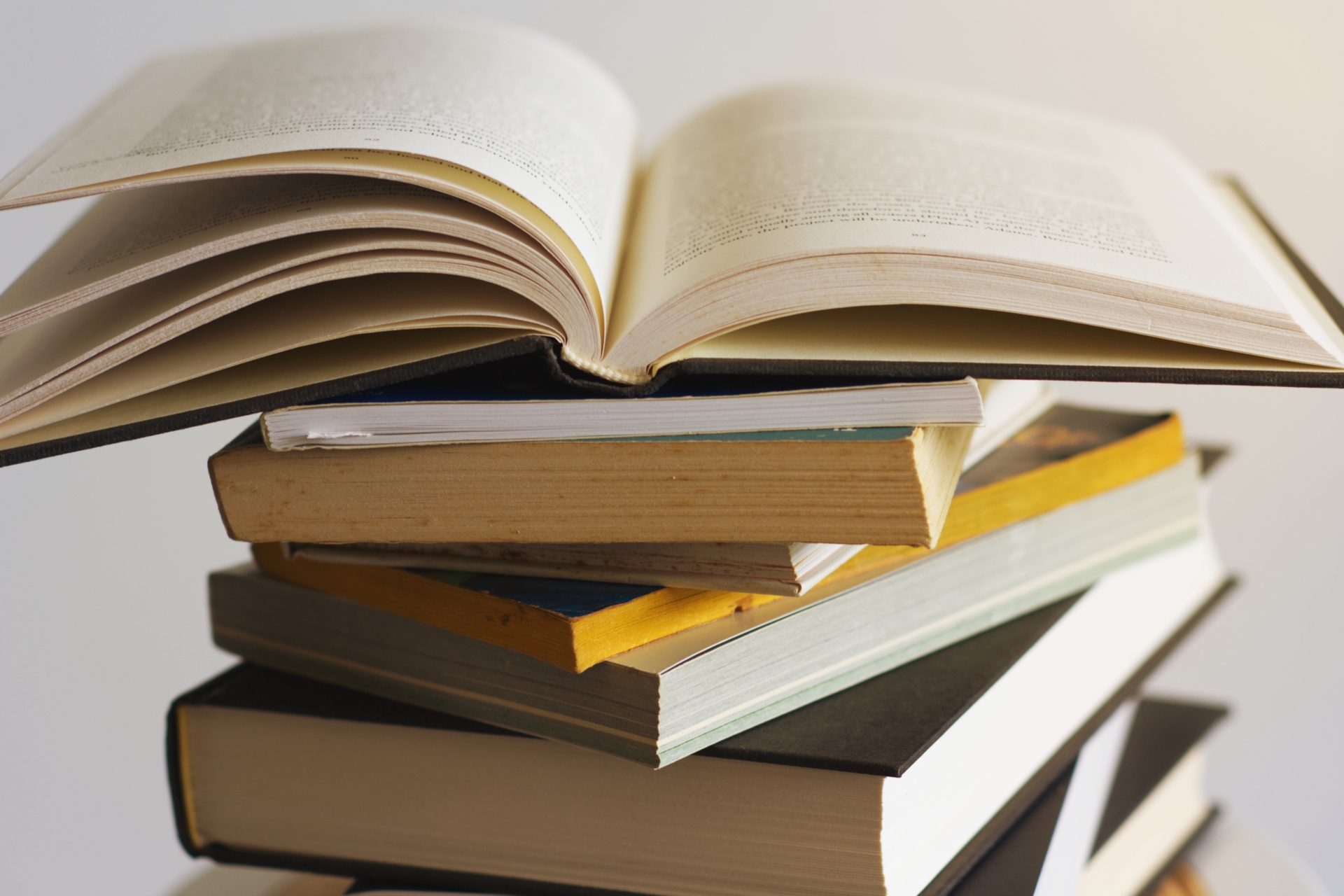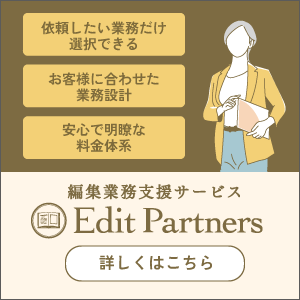2016年8月18日
案内状や暑中見舞いなどに使える「時候の挨拶」一覧と使い方

目次 ▼
この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。
ビジネス文書でも重要な時候の挨拶
時候の挨拶、また季節の挨拶とは、手紙やはがきなどを書く際において、「頭語」の後に続く、文章の冒頭に使用する礼儀文のことです。
使い方としては「時候の挨拶」または「季節の挨拶」が最初にあり、その後に「安否を気遣う挨拶」が続きます。
(※ちなみに頭語とは手紙の冒頭に書く「こんにちは」のような挨拶のこと。)
時候の挨拶は、ビジネス文書、とくに案内状や暑中見舞いなどの書面においても多く用いられるため、ビジネスマナーとして簡単なものは覚えておくとよいでしょう。
ちなみに時候の挨拶とはいいますが、季節を問わず使える言葉もあります。
ビジネス文書としてもお馴染みの「時下」という言葉です。
例)時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
時下とは「このところ」「現在」のような意味を持っているため、いつでも使えるのです。
全て「時下」でいいような気もしますが、季節ならではの挨拶のほうが、少し洗練された印象になるのは否めません。
また、相手を思いやる誠実な印象を与えます。
そこで今回は、月ごとの代表的な時候の挨拶、季節の挨拶をご紹介したいと思います。
1月(睦月)
年賀状や寒中見舞いなど、挨拶状のやり取りが多い季節です。
新春(1/7まで)、二十四節気の「小寒(1/5~6日頃)」や「大寒(1/20~21頃)」など、それぞれ時期によって使用できない季語がありますので、注意しましょう。
ちなみに寒中見舞いは松が明けてから(松の内は一般に1月7日まで)、立春(2/4頃)の前までに届けます。
時候の挨拶
以下の季語に「~の候」「~のみぎり」「~の折」を繋げます。
初春
新春
迎春
小寒
大寒
厳寒
酷寒
極寒
烈寒
甚寒
寒冷
寒風
降雪
冷雨
厳冬
仲冬
例)
新春の候、ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。
季節の挨拶
謹賀新年
寒気厳しき折柄
初春とはいえ
厳しい寒さ
一面の銀世界
寒さ厳しき折柄
例年にない寒さ
いよいよ寒気がつのり
星も凍るような寒い夜
寒気ことのほか厳しく
雪の晴れ間
積雪は軒につかえ
霜柱を踏んで
水道の蛇口も凍る寒さ
ビルの谷間を抜ける木枯らしの音
冬来たりなば春遠からじ
例)寒さ厳しき折柄、皆様にはますますご健勝のほどお喜び申し上げます。
2月(如月)
二十四節気の「立春(2/4日)」や「雨水(2/18~19頃)」 など、時期によって使用できない季語がありますので、注意しましょう。
時候の挨拶
以下の季語に「~の候」「~のみぎり」「~の折」を繋げます。
立春
向春
早春
春浅
春雪
春寒
晩冬
残雪
雪解
余寒
残寒
厳寒
梅花
紅梅
梅月
梅鴬
中陽
節分
寒明け
例)
梅花の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。
季節の挨拶
春まだ浅く
立春とは名のみの寒さ
冬の名残りがなかなか去らず
寒気は冴えかえり
春とは名ばかりでまだ真冬のように寒く
水ぬるむ季節となりましたが
暦の上に春は立ちながら
三寒四暖と申しますが
三寒四温とか言われる季節
いくらか寒さもゆるみ
梅のつぼみもそろそろ膨らみ
何となく春めいて
例)余寒厳しき折柄、まだ寒さ厳しき日が続いております。
3月(弥生)
二十四節気の「啓蟄(3/5~6日頃)」や「春分(3/20~21頃)」など、時期によって使用できない季語がありますので、注意しましょう。
時候の挨拶
以下の季語に「~の候」「~のみぎり」「~の折」を繋げます。
早春
春分
春風
春色
春陽
春情
春晴
春寒
春暖
春雨
浅春
盛春
孟春
仲春
初春
麗日
軽暖
解氷
雪解
弥生
若草
水ぬるむ
春暖快適
例)
早春の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
季節の挨拶
風はまだ寒く
寒さも緩み
春寒しだいに緩み
春暖快適の候
春の彼岸の頃
春色とみに濃く
春寒料峭のみぎり
日増しに暖かさを増し
小川の水もぬるみ
つぼみも膨らむころ
桃の蕾もふくらみ
日増しに暖かくなり
急に春めいて
木々の緑日ごとに色めく季節
若草萌ゆる候
一雨ごとの暖かさ
日毎にのどかになり
菜の花は今が盛り
例)
日増しに暖かさを増し、過ごしやすい季節となりましたが、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
4月(卯月)
時候の挨拶
以下の季語に「~の候」「~のみぎり」「~の折」を繋げます。
春暖
春晩
春日
春風
春和
春粧
春眠
春爛漫
陽春
麗春
暮春
惜春
仲春
桜花
清和
温暖
春風駘蕩
桜花爛漫
花冷え
例)
春風の候、貴社いよいよご盛栄のこととお慶び申し上げます。
季節の挨拶
春陽麗和の好季節
春たけなわ
花曇りの昨今
春もたけなわの日和
花便りも伝わる今日このごろ
うららかな好季節を迎え
春光うららかな
春の愁いにとらわれ
春宵一刻千金の候
春も深くなり
葉桜の季節となり
春も半ばを過ぎ
惜春の思いは深く
若草萌える季節
かげろうもえる季節
例)
春も半ばを過ぎ、葉桜の季節となりました。
5月(皐月)
時候の挨拶
以下の季語に「~の候」「~のみぎり」「~の折」を繋げます。
晩春
残春
惜春
暮春
老春
藤花
葉桜
薫風
陽光
万緑
新緑
青葉
若葉
立夏
初夏
梅夏
向暑
軽暑
微暑
例)
晩春の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
季節の挨拶
新緑の色増す季節
新緑の野山に萌える今日この頃
風薫るこのごろ
風薫る五月の空に鯉のぼりが
若葉の目にしみる候
緑濃く
緑したたる
五月晴れ
大空にこいのぼりの躍るころ
吹く風も夏めいて
青田を渡る風
新茶の香り
牡丹の花が咲き誇り
初夏の風もさわやかな頃となり
深緑の色増す頃
例)
深緑の色増す季節、皆々様お健やかにお過ごしのご様子、なによりと存じます。
6月(水無月)
時候の挨拶
以下の季語に「~の候」「~のみぎり」「~の折」を繋げます。
入梅
梅雨
梅雨寒
梅雨空
長雨
小夏
初夏
立夏
首夏
青葉
深緑
夏秋
麦秋
向暑
薄暑
例)
薄暑のみぎり、皆様にはいよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。
季節の挨拶
さわやかな初夏の季節
梅雨がうっとうしい折から
時候不順の折
うっとうしい梅雨の季節
長かった梅雨もようやくあがり
爽やかな初夏を迎え
初夏の風に肌も汗ばむ頃
樹々の緑深くなり
若鮎のおどる
暑さ日増しに厳しく
空には白い雲が浮かび
暑気日ごとに加わり
日の光も青く
例)
長かった梅雨もようやくあがり、木々の緑も日増しに深くなってまいりました。
7月(文月)
二十四気の小暑(夏至から15日目、7/7頃)〜大暑(7/22頃)の期間を暑中と呼び、暑中見舞いはこの期間に送るのが正式です。
しかし、一般的には、梅雨明けから立秋(8/7頃)まで「暑中見舞い」を送り、それ以降は「残暑見舞い」として送ります。
残暑見舞いは処暑(8/23頃)までに送りましょう。
時候の挨拶
以下の季語に「~の候」「~のみぎり」「~の折」を繋げます。
盛夏
仲夏
猛暑
酷暑
炎暑
大暑
盛暑
向暑
厳暑
極暑
烈暑
炎熱
三伏
例)
盛夏の候、貴社いよいよご盛栄のこととお慶び申し上げます。
季節の挨拶
三伏大暑の候
爽快な夏
まぶしいほどの夏
海山の恋しい季節
楽しい夏休み
連日厳しい暑さ
夏祭りのにぎわうころ
炎暑のみぎり
日々暑さ厳しき折から
涼風肌に心地よく
旱天続きで
草木も生気を失い
土用の入りとなり
近年にない暑さが続き
蝉の声に更に暑さを覚え
一雨欲しいこのごろ
例)
連日厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしですか。
8月(葉月)
二十四節気の「立秋(8/7~8日頃)」や「処暑(8/23)」など、それぞれ時期によって使用できない季語がありますので、注意しましょう。
また残暑見舞いは立秋から処暑までに送りましょう。
時候の挨拶
以下の季語に「~の候」「~のみぎり」「~の折」を繋げます。
残暑
晩夏
残夏
処暑
暮夏
暁夏
残炎
早涼
新涼
秋暑
納涼
初秋
立秋
例)
残暑の候、貴社ますますご隆盛のことと大慶に存じます。
季節の挨拶
残暑厳しき折から
残暑凌ぎ難き候
土用あけの暑さは厳しく
立秋とは名ばかりの暑さ続き
暦の上では立秋ですが
青草を蒸すような強い日射し
残暑なお厳しい折柄
秋暑厳しき折柄
秋にはまだ遠く
秋立つとはいえ
朝夕涼味を覚えるころ
夜空に秋の気配を感じるころ
避暑客の姿も少なくなり
暑さも峠を越しいよいよ秋
虫の声に秋も近づいた事を感じる昨今
まだまだ暑い日が続いておりますが
例)
暦の上では立秋ですがまだまだ暑さが厳しいですね。
9月(長月)
二十四節気の「白露(9/7~8日頃)」や「秋分(9/23)」など、それぞれ時期によって使用できない季語がありますので、注意しましょう。
また、初秋は白露の前日までを指し示します。
時候の挨拶
以下の季語に「~の候」「~のみぎり」「~の折」を繋げます。
初秋
早秋
爽秋
新秋
孟秋
仲秋
秋冷
秋分
秋涼
秋霜
秋色
涼風
早涼
清涼
新涼
野分
白露
例)
初秋の候、皆々様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
季節の挨拶
二百十日も無事に過ぎ
爽やかな季節を迎え
朝夕はめっきり涼しく
朝夕日毎に涼しくなり
虫の音美しい
秋の気配が次第に濃くなって
新秋快適のみぎり
秋色次第に濃く
初雁の姿に秋を感じる頃
野山もにわかに秋色をおび
スポーツの秋を迎え
例)
爽やかな季節を迎え、皆様にはますますご活躍のことと拝察いたしております。
10月(神無月)
時候の挨拶
以下の季語に「~の候」「~のみぎり」「~の折」を繋げます。
秋涼
秋冷
秋晴
秋麗
秋月
秋雨
清秋
錦秋
仲秋
中秋
爽秋
菊花
紅葉
涼寒
朝寒
初霜
寒露
例)
秋涼のみぎり、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
季節の挨拶
秋の夜長
さわやかな好季節
さわやかな秋晴れの続く
秋涼爽快のみぎり
秋気肌にしみ
秋涼爽快の候
秋色日毎に深まり
日増しに秋も深まり
燈火親しむの候
木々の梢も色づいて
実りの秋となり
灯火親しむの候
空は深く澄み渡り
夜長の頃となり
冷気は日増しに加わり
スポーツの秋
味覚の秋
天高く馬肥ゆるの候
例)
秋の夜長、虫の音が心地よい季節となりましたが、お元気でいらっしゃいますか。
11月(霜月)
時候の挨拶
以下の季語に「~の候」「~のみぎり」「~の折」を繋げます。
晩秋
季秋
霜秋
深秋
暮秋
深冷
夜寒
向寒
氷雨
菊薫る
菊花
残菊
落葉
初霜
初冬
立冬
例)
深秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
季節の挨拶
菊薫る今日このごろ
菊薫る候
ゆく秋の寂しさ身にしみるころ
秋気いよいよ深く
秋も一段と深まり
鮮やかな紅葉の候となり
舗道に落ち葉が散る頃
小春日和の今日此頃
朝夕一際冷え込むころ
吐く息も白くなり
夜寒の折柄
冷気日ごとに加わり
日毎冷気が加わり
追々寒さ向かいますが
冷雨が降り続く
例)
秋も一段と深まり、日だまりの恋しい季節となりました。皆様お変わりなくお過ごしですか。
12月(師走)
時候の挨拶
以下の季語に「~の候」「~のみぎり」「~の折」を繋げます。
師走
寒冷
初冬
歳末
歳晩
明冷
初雪
霜夜
霜寒
新雪
極月
孟冬
忙月
短日
厳寒
短日
寒気
例)
歳末の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
季節の挨拶
寒気厳しき折柄
寒気いよいよ厳しく
めっきり寒くなり
あわただしい師走となり
師走に入って一段と寒く
年の瀬もいよいよ押し詰まり
歳末何かとご多端の折柄
木枯らし吹きすさぶころ
今年もいよいよおしつまり
年末御多忙の折から
年もせまり何かとご繁忙のこと
寒さもひとしお身にしみるころ
例)
木枯らしが吹きすさぶころとなりましたが、皆様いかがお過ごしですか。
時候の挨拶/季節の挨拶一覧 まとめ
全てを覚える必要はありませんが、代表的な時候の挨拶や二十四節気などは覚えておくと何かと便利です。
ちなみに、テレビドラマや小説などでよく見かける「前略」という頭語は、挨拶などを略することをいいます。
ですので、「前略、時下益々〜」という表現は間違いです。気をつけましょう。
ちなみに文章の冒頭に挨拶があるのと同じく、結びにも挨拶があります。
結びの挨拶とは、「主文」の後に続け手紙を締めくくるための言葉で、送る相手や手紙の内容によって使い分け、簡潔に書き上げることが大切です。
結びの挨拶はいずれまたご紹介したいと思います。