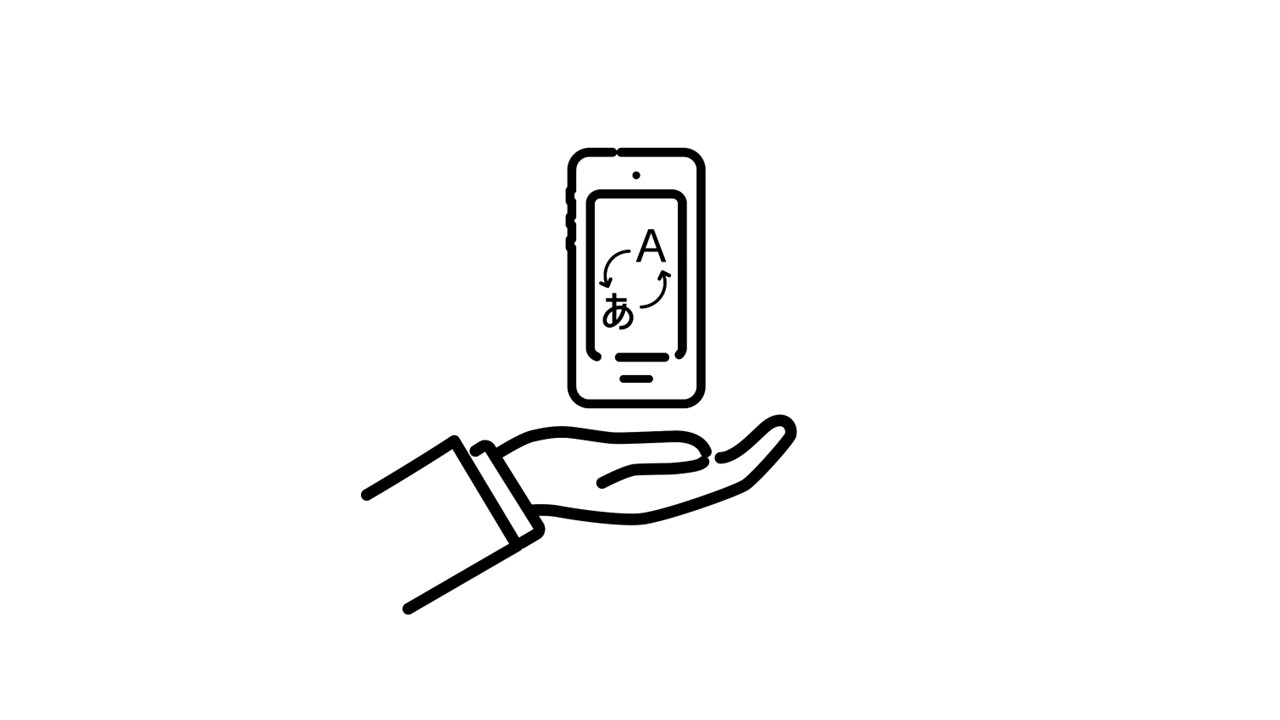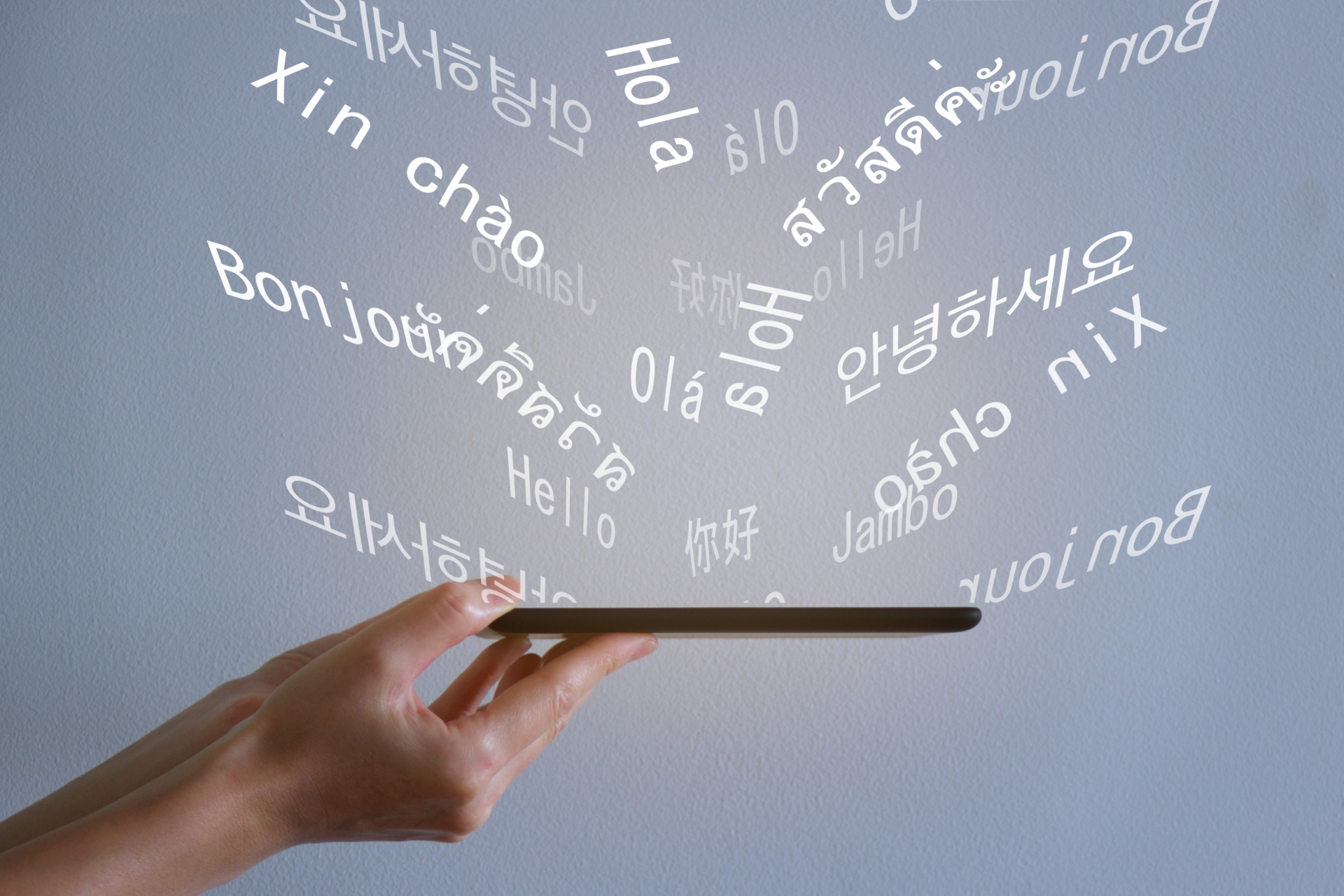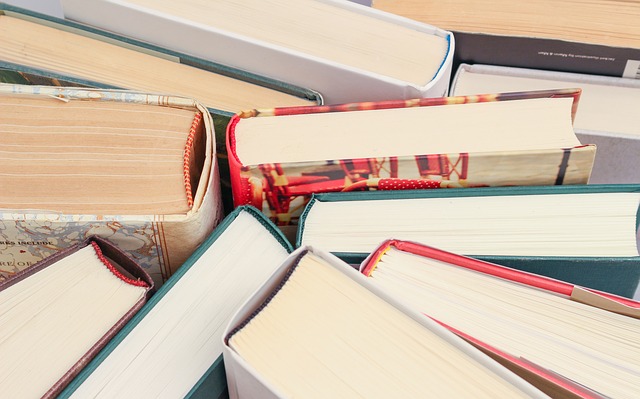2025年5月22日
取扱説明書の作成に欠かせない6つのポイントとは?

目次 ▼
この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。
取扱説明書は、多くの場合、製品に関する知識がない一般の消費者やユーザーが読むものです。そのため、誰もが迷わず、正しく安全に使用できるように配慮することが重要です。
万が一、取扱説明書に不備や誤りがあると、思わぬトラブルや事故につながる可能性があります。そのリスクを避けるためにも、取扱説明書の作成には十分な時間をかけ、慎重に内容を検討する必要があります。
今回は、取扱説明書を作成する際に押さえておきたいポイントをご紹介します。
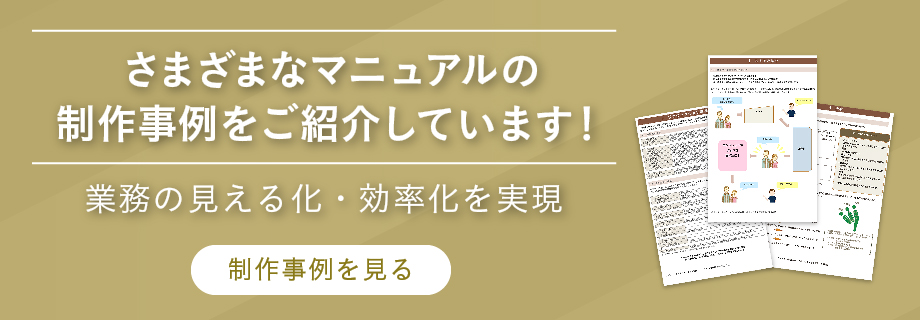
取扱説明書作成の6つのポイント
1.イラストや写真を活用する
「使いやすいマニュアルとは?作成時に気をつけたい5つのポイント」でもご紹介したように、文字だけの取扱説明書では操作のイメージが伝わりにくく、具体的にどの部分をどのように操作すればよいのかがわからなくなることがあります。
そのため、製品のイラストや写真は積極的に活用し、ユーザーが視覚的にも理解しやすい構成を心がけましょう。
製品のどの部分を説明しているのかがわかるよう、全体との位置関係を示したり、該当箇所を強調するなどの工夫を加えることで、より直感的に理解できるようになります。
2.操作の結果を明記する
取扱説明書には、操作手順だけでなく、その操作の結果がどうなるのかを明確に記載することも重要です。
結果の記載がないと、ユーザーは正しく操作できているのか判断できず、不安を感じたり、誤操作に気が付けない可能性があります。
操作した後にこのような結果になれば正しく、このような結果になると間違っているということが明確にわかるようにしましょう。
例えば、「ボタンを押す」「コードを差し込む」といった操作に対しては、「ボタンを押して、ランプが青色に点灯していることを確認する」「カチッという音がするまでコードを差し込む」というように、ユーザー側で正しく操作できていることを判断できる基準があるとよいです。
3.必要な情報にすぐアクセスできるようにする
最初から取扱説明書をすべて読み込むユーザーは少なく、多くの場合は、操作中に疑問や問題が生じた際に必要な箇所を探して読みます。
そのため、困ったときに、必要な情報がすぐに探せるよう、検索性の高い構成が求められます。
目次を見れば必要なページがすぐに特定でき、ページ内でも必要な情報が一目でわかるような構成にしましょう。
また、製品の機能をただ羅列するのではなく、目的別・シーン別・操作の流れ別に分類するなど、ユーザーのニーズに合わせた構成を意識することも効果的です。
4.PL法に基づき警告・注意事項を明記する
PL法(製造物責任法)とは、製品の欠陥により生命や身体、財産に損害が生じた場合、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができる法律です。
ここで言う「欠陥」とは、製造や設計上の不備だけでなく、危険性に対する注意喚起や安全に使用するための情報が不足している「指示・警告上の欠陥」も含まれます。
そのため、取扱説明書には適切な警告や注意事項を明記する必要があります。PL法に関しては法務部が担当するケースが多いですが、取扱説明書を作成する担当者もPL法について必ず理解しておきましょう。
5.トラブルシューティングを設ける
万が一、トラブルや不具体が発生した際に備えて、原因の特定と対処法をまとめた「トラブルシューティング」の項目を設けましょう。
「エラーが表示されたときは」「動かなくなったときは」など、よくあるトラブルを想定し、対処法とあわせて掲載することで、ユーザー自身で問題を解決しやすくなります。
あわせて、FAQ(よくある質問)も記載しておくと、問い合わせ件数の軽減にもつながります。
6.索引を作成する
ユーザーが必要な情報にすばやくアクセスできるよう、目次に加えて、巻末に索引を設けることも有効です。
その際、単に目次の内容を五十音順やアルファベット順に並べるだけでなく、ユーザーが思い浮かべる可能性のあるキーワードを盛り込んだり、複数の検索語からでも目的の情報にたどり着けるような設計を意識することがポイントです。
まとめ
今回は、取扱説明書を作成する際に意識すべきポイントをご紹介しました。
製品の種類や業界によって記載すべき内容は異なりますが、共通して重要なのは「ユーザーの視点に立つこと」です。誰でも正しく安全に製品を使えるようにすることが、取扱説明書の最も大きな役割と言えます。
記載内容に誤りや抜け漏れがあると、思わぬトラブルや重大な事故につながるおそれがあります。取扱説明書を作成する際は、ユーザーが内容を正しく理解できるか、不足や誤りがないかを入念に確認しましょう。