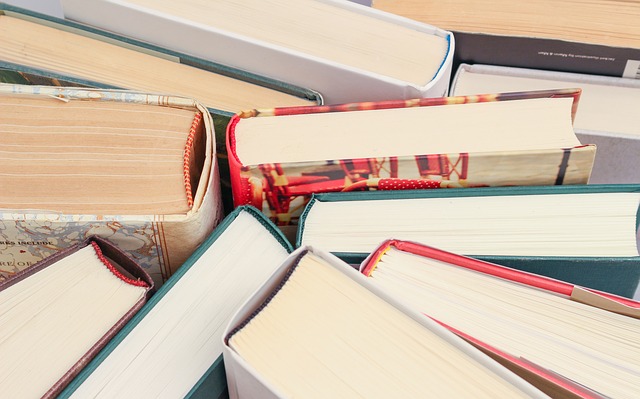2024年8月14日
もうネタ探しに悩まない!機関誌の企画例10選

目次 ▼
この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。
機関誌制作に携わる皆さんの中には、毎号の企画やネタ探しに頭を悩ませているという方も多いのではないでしょうか?月に一回、3か月に一回、半年に一回、など定期的に発行していると、どうしても企画がマンネリ化してしまいがちですよね。
しかし、例えどんなにすばらしいデザインであったとしても、内容が充実していなければ読者を満足させることは難しく、多くの人に読んでもらうためには、企画やコンテンツの質が非常に重要です。
そこで今回は、機関誌の企画例をご紹介いたします。
機関誌とは?
機関誌とは、学会、協会、研究機関、非営利組織などが発行している定期刊行物のことを指します。
「医療」「福祉」「建築」など、団体や協会ごとに特定の分野にテーマが絞られており、主に個人会員や会員企業に向けた活動報告や情報交換を目的として発行されています。
読まれる機関誌を作るための企画立案のポイント
発行目的と読者対象を意識する
まずは機関誌を発行する目的を明確にし、その目的を達成するために最適な企画や伝えるべき内容を検討しましょう。
また、「誰に届けたいのか」という読み手を意識することも重要です。基本的に機関誌は会員向けの冊子ではありますが、会員の中でもどのような属性の人が多いのか、どのような情報を求めているのかに注目することで、企画の内容や見せ方が見えてきます。
タイムリーな情報を取り入れる
季節や時事に合わせた内容を取り入れることで、より読者の関心を惹きやすくなります。定期的に発行される機関誌だからこそ、最新の情報を届けやすいというメリットがあります。
ただし、発行頻度が半年に一度や年に一度の場合、制作時には最新だった情報が発行時には古くなってしまうことも考えられます。読者の手元に届くタイミングを考慮し、企画内容を検討するとよいでしょう。
また、よりリアルタイムに情報を届ける手段として、Web媒体を活用するのも一つの方法です。
効果測定を行う
どのような企画が求められているのかわからない場合は、効果測定を行い、読者の声を直接聞いてみるとよいでしょう。紙媒体の場合は読者アンケートやヒアリング、Web媒体の場合はWeb解析ツールを使った閲覧数や閲覧時間のチェックなどが有効です。
効果測定を通じて良かった企画とそうでない企画を振り返り、PDCAサイクルを回していくことで、読者満足度の高い機関誌へとブラッシュアップされていきます。

機関誌の企画例・ネタ 10選
ここからは、機関誌でよく見られる記事企画の例やアイデアをご紹介していきます。機関誌は一般的に堅い内容が多いですが、読者の興味を惹くためには、企画の見せ方を工夫することが重要です。
1.巻頭言
巻頭言は、冊子の冒頭に掲載される文章で、序文としての役割を果たします。特定のテーマや内容に縛られることはなく、挨拶や最近のトピックス、特集内容に関連した話題が多く用いられます。
2.対談・鼎談(ていだん)
対談は二人、鼎談は三人で行われる会話形式の記事です。
普段は話す機会が少ない会員同士や、関連企業の担当者同士が話すことによって、読者が共感できる話題や新たな発見が生まれることもあります。堅い内容や専門的なテーマであっても、対話形式にすることで読者の興味を惹きやすくなるでしょう。
3.座談会
座談会も機関誌の企画としておすすめです。テーマを設定し、それに関連するメンバーを集めることで、記事の方向性としてもまとまりやすく、目玉企画にもなり得ます。
インタビューや対談に比べるとカジュアルな雰囲気のため、参加者も発言しやすく、より本音を引き出しやすくなるでしょう。
4.インタビュー
会員や関連企業、または業界に関連のある著名人にインタビューを行い、記事としてまとめます。関連企業の社長や会長、大きなプロジェクトに関わった会員など、記事として魅力的な人物に話を聞くことで、読者の関心を惹くことができます。
特に、業界に関連のある著名人へのインタビューはそれだけで目玉企画となり、多くの人に読んでもらえるきっかけになります。取材依頼や撮影など、準備や作成に時間がかかる企画ではありますが、その分読者に満足してもらえる企画とも言えます。
5.時事に関するトピックス
時事に関するタイムリーな話題は、読者の興味を惹きやすいテーマです。よく取り上げられる内容としては、業界に関連する最新技術や社会の動向、法改正などが挙げられます。
流動的で変化のある内容のため、連載というよりは特集企画として取り上げられることが多いです。
6.活動報告
先ほど機関誌の発行目的をご紹介しましたが、その役割からも機関誌の企画として活動内容の報告は欠かせません。総会や講演会、セミナー、展示会、学会などの活動報告は、多くの機関誌で定番の企画です。
ただ単に開催日時や概要を載せるだけでなく、実際の活動を取材し写真撮影をしたり、参加者から感想を聞くなどして、活動内容の詳細や当日の様子などを掲載するとよいでしょう。活動内容を読者に広く知ってもらうことで、次回の参加へとつながることもあります。
7.会員企業レポート
会員企業の取り組みや活動状況を取材し、記事にまとめます。
同じ業界であっても企業同士の横のつながりを構築する機会はあまり多くないため、こうした企画で他の企業の取り組みを知ることができるのは、読者にとって貴重な情報源となるでしょう。
8.海外情報
業界に関連する海外の情報を掲載することもあります。海外に拠点を持つ会員企業があればテーマを決めて執筆依頼をしたり、海外研修を行った会員に研修レポートとして記事を書いてもらうケースもあります。
普段海外に関する情報はなかなか入手しにくいため、読者の関心が高い企画と言えます。
9.エッセイ
特定のテーマを設けず、執筆者の体験や考えなどを自由に綴るエッセイも、機関誌においておすすめの企画です。季節の話題や世間の動向、自身の活動など、エッセイではさまざまなトピックスを取り上げることができます。
機関誌はどうしても内容が堅くなってしまいがちですが、エッセイを入れることによって誌面にメリハリが生まれ、読者にとっても読みやすくなるでしょう。
10.書籍紹介
業界に関連する書籍を紹介するコーナーも、機関誌の企画としておすすめです。関連書籍以外にも、話題になっているビジネス書やおすすめの小説などを紹介してもいいかもしれません。
編集部が毎号選んでいるとネタ不足になってしまいがちなため、その号の執筆者にそれぞれおすすめの一冊を選んでもらうのも方法の一つです。
まとめ
今回は、機関誌の企画例を10個ご紹介しました。
企画を考える際には、機関誌の発行目的や読者対象を意識することが大切です。継続的に発行しているとどうしてもネタ切れやマンネリに陥ってしまいがちですが、読者満足度を高めるためにも、企画立案にはしっかりと時間をかけ、魅力的な機関誌を作っていきましょう。
他の機関誌を参考にするのも、アイデアを得るための一つの方法です。ぜひ参考にしてみてください。
日本で唯一の機関誌専門ポータルサイト「キカンシネット」