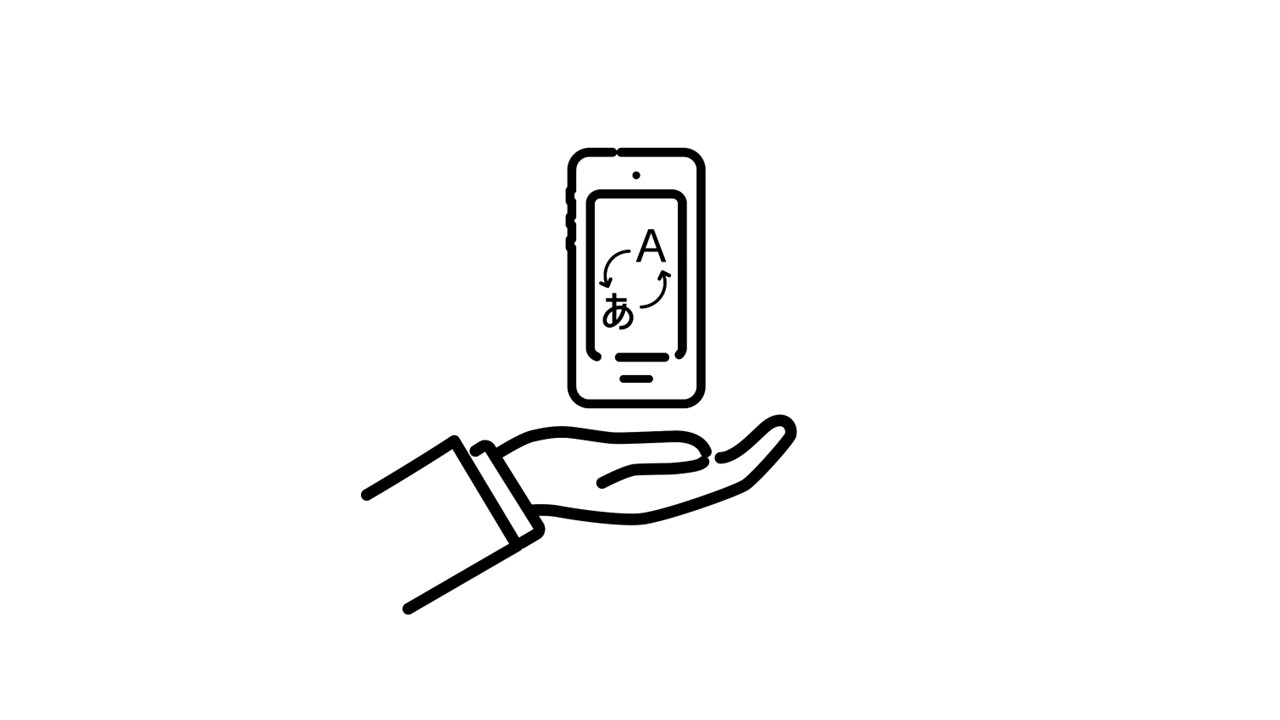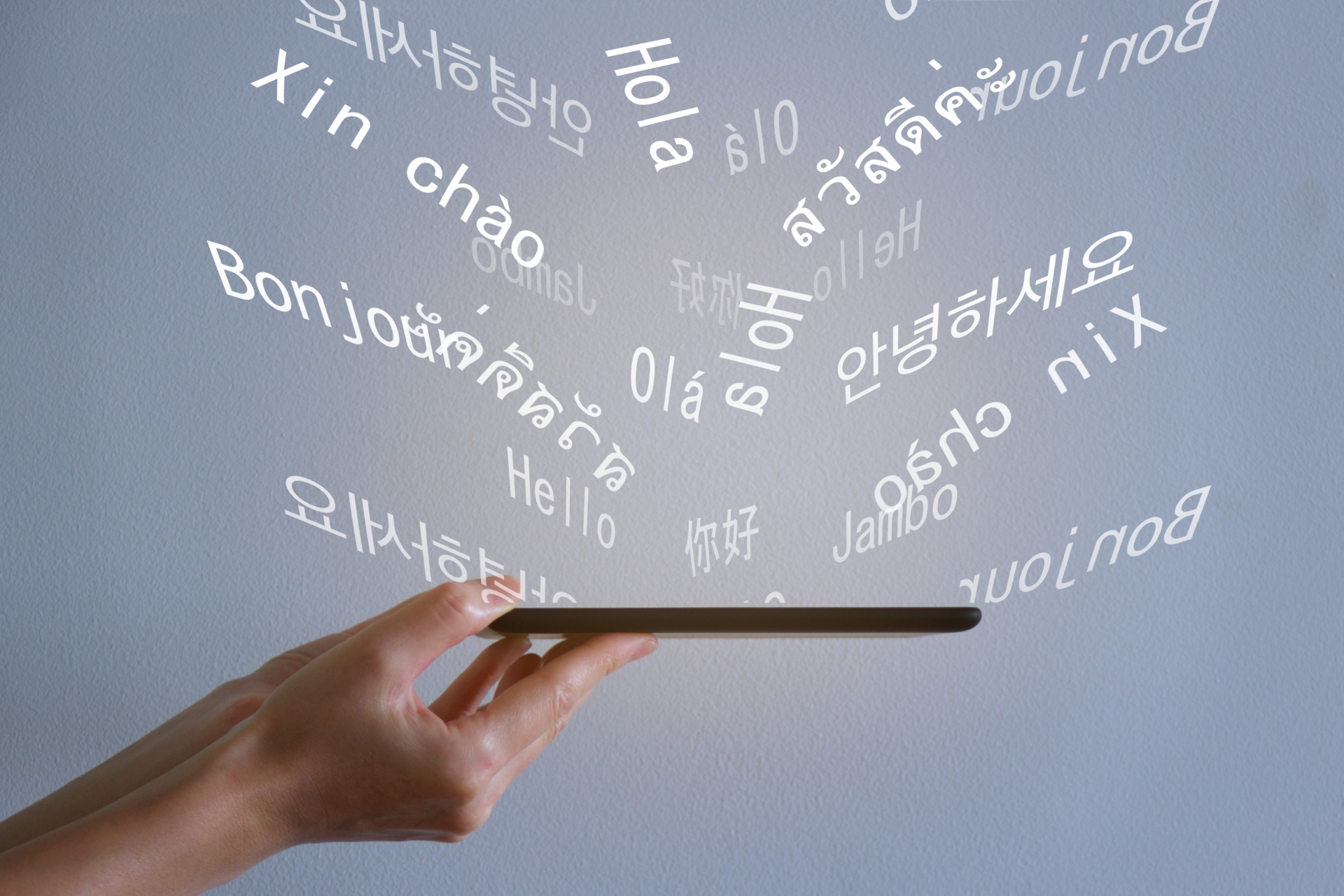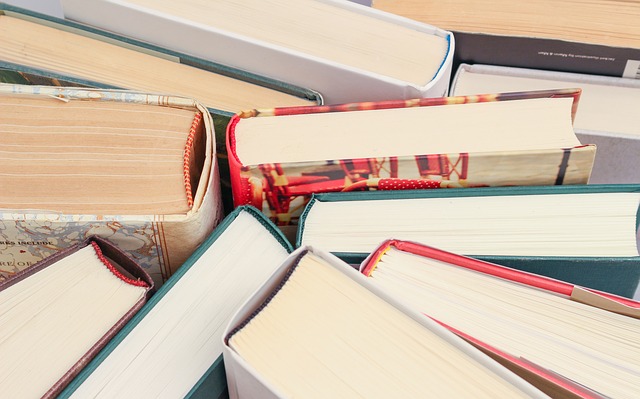2024年12月19日
マニュアルと手順書はどう違う?手順書の作り方とポイント

目次 ▼
この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。
業務効率化や人材育成において重要な役割を果たすマニュアル。「業務マニュアル」「営業マニュアル」「操作マニュアル」など、さまざまな種類が存在しますが、同じように「手順書」という言葉も耳にしたことがあるのではないでしょうか?
「どちらも似ていて違いがよくわからない」「同じ意味で使っている」という方も多いかもしれませんが、実は微妙な違いがあります。
そこで今回は、マニュアルと手順書の違いについて解説し、さらに手順書の作り方を詳しくご紹介いたします。
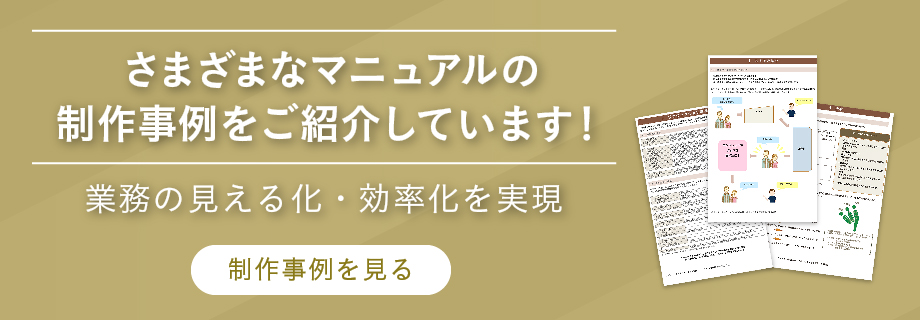
マニュアルと手順書の違い
マニュアルの中に手順書が含まれる場合もありますが、基本的には大きく分けて「目的」「役割」「内容」という3つの違いがあります。
| マニュアル | 手順書 | |
| 目的 | 人材育成、業務課題の達成 品質の向上、業務効率化 | 業務品質の維持、ミスの防止 |
| 役割 | 業務の全体像を示し、理解を深める | 誰でもミスなく同じように作業ができる基準を示す |
| 内容 | 作業手順のほか、業務の基本知識、 概要・背景・ルールなど(比較的情報量が多い) | 細かい業務手順、ポイント、 品質基準、注意事項など(比較的情報量が少ない) |
目的
まず、マニュアルと手順書では、作成の目的が異なります。
マニュアルは、業務全体の理解を深めることを目的としており、人材育成や品質向上、課題解決や目標達成などを目指します。一方、手順書は、業務品質の維持やミスの防止を主な目的としており、具体的な作業の安定的な遂行を重視します。
つまり、マニュアルは組織全体や業務全体の目標達成を目指すのに対し、手順書は個々の作業の精度を高めることを目指していると言えます。
役割
マニュアルの役割は、業務の全体像を示し、業務に対する理解を深めることです。そのため、手順やフローに加えて、業務の背景やプロセスなども盛り込み、業務全体を俯瞰的に理解できるようにサポートします。
一方、手順書の役割は、誰でもミスなく同じように作業ができる基準を示すことです。理解を深めることよりも、実際の業務を問題なく遂行できるようにすることに重点を置いています。
内容
目的や役割の違いにより、マニュアルと手順書では記載する内容や情報量が異なります。
どちらも業務に関する内容を記載する点は同じですが、マニュアルは作業手順だけでなく、業務の概要、背景、ルール、ノウハウなど、業務全体に関する広範囲な情報を含みます。業務の全体像を示す要素の一つとして作業手順が載っているというイメージです。
一方、手順書は作業手順に重点を置き、フローや品質基準、注意事項など、より詳細で具体的な内容を記載します。マニュアルに比べて情報の範囲は限られており、深く掘り下げた内容となっているのが特徴です。
手順書作成のポイント
誰が読んでもわかるように書く
手順書は、新入社員や異動してきた社員など、業務に不慣れな人が主に使用するため、誰が読んでも理解できる内容にすることが大切です。 略語や専門用語はできるだけ避け、初めてその業務に取り組む人でも理解しやすい表現を心がけましょう。
また、文字だけでは手順が把握しづらいこともあります。フロー図や作業中の写真、操作画面のキャプチャなど、視覚的な情報を取り入れることで、読み手側も作業手順をイメージしやすくなります。業務内容によっては、動画を活用するのも効果的です。
手順書は、新人だけでなく、経験者が困った際に参照されるケースもあるため、直感的に理解できるよう、読み手の視点に立って言い回しや情報の伝え方を工夫しましょう。
具体的に詳細を書く
手順書では、具体的で詳細な記述が求められます。「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」という5W1Hを意識して、必要な情報を盛り込みます。
例えば、「ライトが赤く点滅したら電源ボタンを5秒間押す」のように、数値や見た目の目安も細かく記載することで、作業をより正確に進めやすくなります。
また、作業を実行した結果がどうなるか、正しい結果と間違いを示す指標を記載することも重要です。
情報を盛り込みすぎない
手順書は、詳細な情報を具体的に記載することが重要ですが、業務の背景やプロセスなど、業務手順以外の情報を盛り込みすぎてしまうと、本来伝えたい情報がぼやけてしまう可能性があります。
手順書の目的は、業務の品質維持やミスの防止であるため、記載する情報を絞り、簡潔にまとめましょう。業務の詳細な背景や補足情報が必要な場合は、マニュアルと併用するのも一つの方法です。
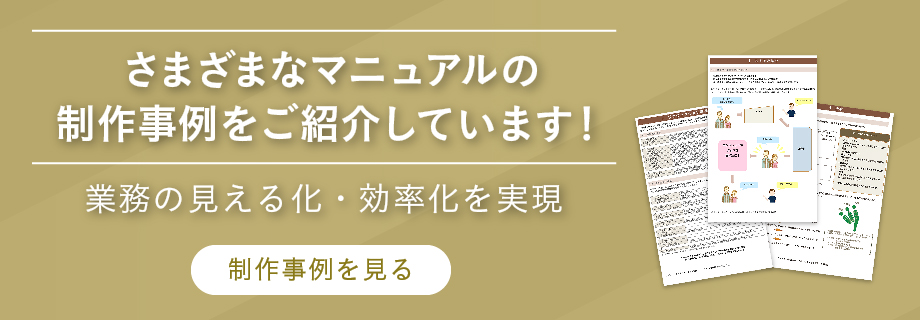
手順書の作り方
1.業務を洗い出し、情報を整理する
マニュアルの場合はまず初めに目的や記載範囲を決める必要がありますが、手順書の場合はすでに「誰でもミスなく同じように業務を遂行する」という目的と、記載する業務手順の範囲が決まっているため、まずは業務内容を洗い出し、情報を整理することから始めます。
具体的には、作業工程ごとに必要な作業を抽出し、カテゴリ分けや時系列順に並べます。手順書に必要な主な情報は以下のとおりです。
・業務の手順
・各工程の目的
・各工程に必要な準備や道具
・具体的な作業内容やポイント
・合否の判断基準
・注意事項、禁止事項
・イレギュラーな事態が起きた場合の対処方法
2.構成を作成する
洗い出した情報を整理したら、続いては手順書全体の構成を作成します。作業工程ごとの階層化や見出しの作成など、目次を作るイメージで構成を練っていくと次第に手順書全体の骨組みが見えてきます。
この段階で、初めにリストアップした作業内容の取捨選択や抜け漏れをチェックします。伝えたいことが明確に伝わるよう、不要な情報は削り、シンプルな構成を意識しましょう。
3.原稿作成
構成ができたら、時系列に沿って原稿を作成します。各工程における具体的な手順やポイントなどを解説していきますが、冗長にならないように、できるだけ短く端的にまとめることを意識しましょう。見出しや箇条書きを活用すると、さらにわかりやすくなります。
必要に応じて、実際に業務を行っているメンバーからのヒアリングも行います。
▼ヒアリングの流れや質問例は、以下の記事で詳しくご紹介しています。
図や写真、イラストなどもこの段階で準備しておきましょう。一から作成するのが難しい場合にはテンプレートを活用するのもおすすめです。
4.内容をチェックしてもらい修正する
作成した手順書は、実際に使用する従業員にチェックしてもらいましょう。わかりにくい部分や実際の作業との乖離がないかどうかフィードバックをもらいます。複数人で確認を行うことで、誤字脱字などの細かいミスを見つけやすくなります。
修正点があれば随時対応し、改善を進めていきます。問題がなければ手順書の運用を開始しますが、マニュアルと同じく一度作成したらそれで終わりではありません。定期的に見直しを行い、作業内容の変更・追加・削除など常に最新の情報を反映させることが重要です。
▼マニュアルの作り方については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
まとめ
今回は、マニュアルと手順書の違いと、手順書の作り方やポイントについてご紹介しました。
マニュアルと手順書の違いを理解しておくことで、手順書に盛り込むべき情報が明確になり、内容がブレることなくスムーズに作成を進めることができます。
手順書には、業務の効率化や品質の維持、ミスの防止といったさまざまなメリットがあります。ぜひ今回の記事を参考に、効果的な手順書作成に取り組んでみてください。