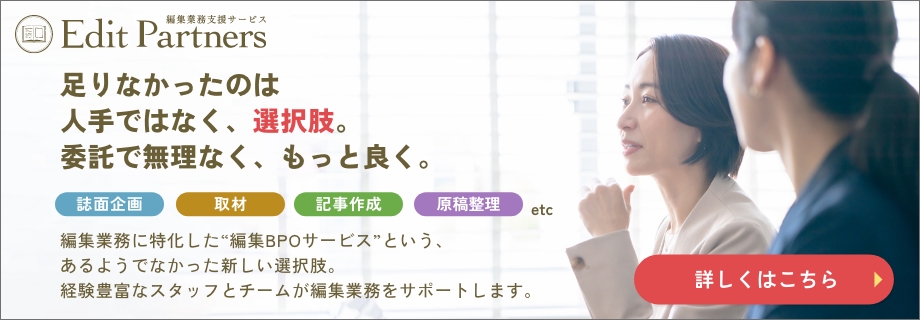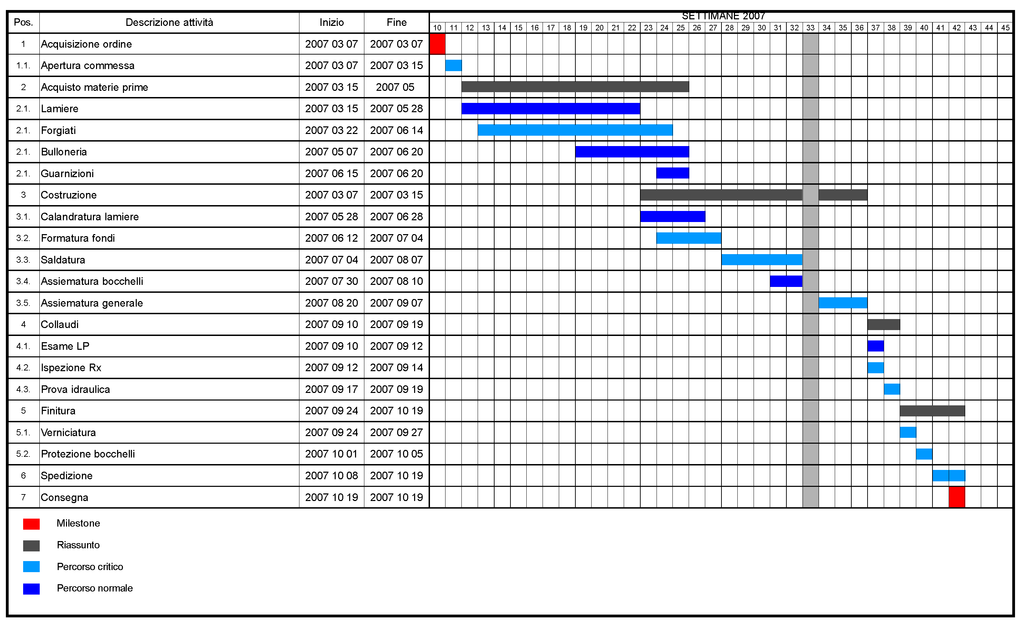2025年4月11日
誤字脱字を防ぐ9つのチェックポイントとは?原因と対策を解説
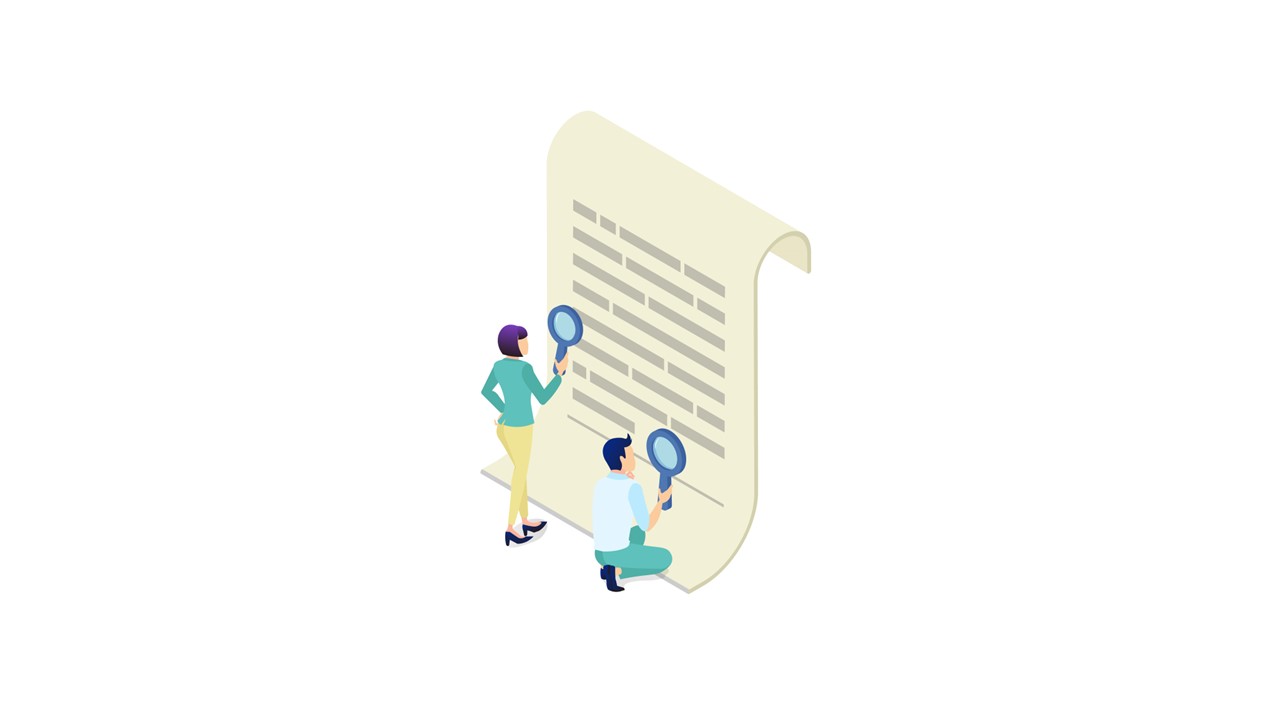
目次 ▼
この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。
文章を書く際、どれだけ注意していても、誤字や脱字はどうしても発生してしまうものです。後からミスを発見したり、読者から指摘を受けたという経験がある方も少なくないのではないでしょうか?
誤字脱字があると、文章が読みにくくなるだけでなく、媒体や発信者への信頼を損ねてしまうおそれもあります。
そこで今回は、誤字脱字が起きる原因と、チェック時に押さえておきたいポイントをご紹介いたします。
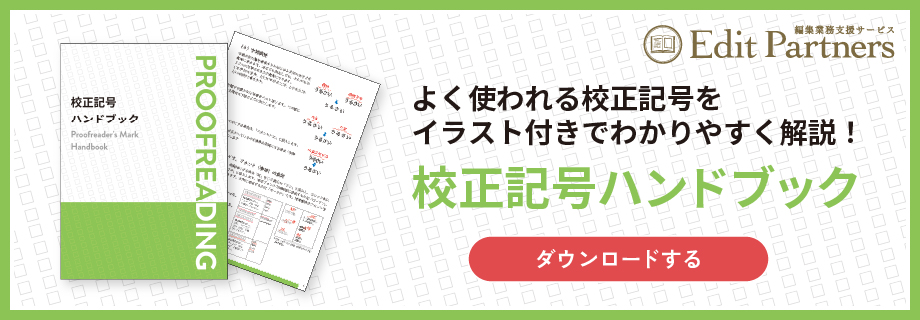
「誤字」「脱字」「衍字」とは?
「誤字脱字」と一括りにされることが多いですが、実際にはそれぞれ意味が異なります。
「誤字」は、その名のとおり、誤った文字を使用することを指します。例えば、漢字の誤りや固有名詞の表記間違い、デジタルデバイスによる変換ミスなどが該当します。
一方で、「脱字」とは、文章中で本来必要な文字が抜け落ちてしまっている状態を指します。送り仮名や助詞の抜け漏れなどが脱字の典型です。
また、誤字脱字とあわせて「衍字(えんじ)」という言葉もよく使われますが、「衍字」とは、文章中に不要な文字が含まれている状態を指します。推敲の過程で余計な文字が残ってしまうケースが多いです。
(例)誤字:明日は友達と映画をミニ行く。
脱字:明日は友達と映を見に行く。
衍字:明日は友達と映画を見にに行く。
誤字脱字が発生する主な原因
誤字や脱字が発生する背景には、さまざまな原因があります。原因が一つではないからこそ、起こりうる原因を知っておくことで、事前に注意すべきポイントが見えてきます。
1.入力ミス
PCやスマートフォンで文章を入力する際、誤って隣のキーを押してしまうことがあるかと思います。特に急いでいるときや長文を入力しているときは、こうしたミスが発生しやすく、なおかつミスに気が付きにくいため、そのまま誤字脱字が残ってしまうことが多いです。
(例)×ありがとうございまうs。
○ありがとうございます。
2.変換ミス
PCやスマートフォンの自動変換機能によって、意図しない単語や漢字に変換されてしまうことがあります。特に同音異義語では変換ミスが発生しやすいため、変換候補をよく確認することが重要です。
(例)×五時脱字 ○誤字脱字
×スピードが早い ○スピードが速い
3.誤用・誤認識
よく使う言葉や慣用句でも、意味や表記を誤って覚えていることがあります。こうした誤用や思い込みも誤字脱字の原因です。また、「シミュレーション」「エンターテインメント」などの英語やカタカナは、発音に引っ張られて誤表記しやすい傾向があります。
これらはそもそも覚え間違いによって発生するため、書き手自身では気が付きにくく、手書きの場合はより一層の注意が必要です。
(例)×少しづつ ○少しずつ
×耳触り ○耳障り
×シュミレーション ○シミュレーション
4.タイポグリセミア現象
タイポグリセミア現象とは、単語の最初と最後の文字さえ合っていれば、間の文字が多少入れ替わっていても正しく読めてしまう現象のことです。
例えば、以下の文章を読んでみてください。
こんちには みさなん おんげき ですか? わしたは げんき です。
この ぶんょしう は いりぎす の ケブンッリジ だがいく の けゅきんう の けっか にんんげ は もじ を にしんき する とき その さしいょ と さいご の もさじえ あいてっれば じばんゅん は めくちちゃゃ でも ちんゃと よめる という けゅきんう に もづいとて わざと もじの じんばゅん を いかれえて あまりす。
よく見ると単語の順番がめちゃくちゃであるにもかかわらず、私たちは意味が通じる文章として読むことができてしまいます。これは人間の脳が、単語を文字列として視覚的に認識し、知っている言葉を瞬時に補完しているためです。
このタイポグリセミア現象によって、誤字脱字の見落としが起こりやすくなってしまうため、チェックする際にはこのような現象が起きることを意識しておくとよいでしょう。

誤字脱字をチェックする際のポイント
1.誤字脱字がある前提でチェックする
どんなに完璧な文章だと思っていても、実際には誤字脱字がたくさんあった…というのはよくあるケースです。「大丈夫だろう」という思い込みが間違いを見落とす原因にもなるため、常に誤字脱字がある前提でチェックすることが重要です。
よくある間違いや過去のミスなどの傾向をつかみ、特に注意が必要な箇所を重点的に確認するのも効果的です。
2.内容を読もうとしない
文章の内容を読みながら誤字脱字をチェックしようとすると、どうしても意味や文脈に意識が向いてしまい、タイポグリセミア現象によって誤字脱字に気づきにくくなります。
誤字脱字をチェックする際は、内容を読むのではなく、文節や単語単位で区切るなどして、一文字ずつ丁寧に確認しましょう。
3.音読する
実際に声に出して読み上げることで、目で追っているだけでは気づきにくい誤りや違和感が見つかることもあります。
自分で音読する以外にも、音声読み上げソフトを利用するのもおすすめです。
▼以下の記事では、無料で使える音声読み上げソフトをご紹介しています。
4.プリントアウトする
PCの画面上だけでチェックしようとすると、スクロールやページの切り替え時に見落としが発生しやすくなります。たとえPCで作成した文章であっても、一度紙にプリントアウトして確認することをおすすめします。
プリントアウトすることで、ペンやマーカーで印をつけながら、一文字ずつ丁寧に目で追って確認できるため、より正確に誤字や脱字をチェックすることができます。
また、途中で確認作業を中断した場合でも、印をつけておけば確認済みの箇所がすぐにわかるため、チェック漏れの防止にもつながります。
5.数字や固有名詞は入念にチェックする
数字や固有名詞は、表記に間違いがないか、特に念入りにチェックする必要があります。
具体的には、
・会社名
・人名
・住所
・電話番号
・商品名
・価格
・日付
・数値、データ
などが挙げられますが、これらは間違いが発生すると発行元の信用に関わったり、大きな問題に発展するおそれがあります。
これらは一見すると誤字脱字に気づきにくいですが、一文字ずつペンで印をつけたり音読することで、間違いを見つけやすくなります。数字を音読する際は「カンマ」や「円」などの記号も含めて読み上げるのが効果的です。
6.一度にチェックする項目を絞る
文章を確認する際、誤字脱字のほかに、内容の確認や表記ゆれの確認など、さまざまな項目をチェックするかと思います。
その際、誤字脱字、原稿との突き合わせ、内容の確認など、一度にすべての項目をチェックしようとすると、集中力が分散し、間違いを見落としやすくなってしまいます。特に、校正と校閲は同時に行おうとすると、表記の確認と内容の確認を並行して行うことになるため、精度が落ちてしまいます。
まずは誤字脱字だけに絞って確認し、次に内容のチェックを行う、など項目ごとに分けてチェックするのがおすすめです。
▼校正と校閲の違いについては、以下の記事でご紹介しています。
7.複数人でチェックする
一人でチェックしていると、どうしても誤字脱字を見落としてしまうことがあります。特に自分で書いた文章は、どうしても客観的な視点で見ることが難しいため、可能であれば第三者にチェックしてもらうとよいでしょう。
時間がない場合は、数字や固有名詞など、絶対に間違ってはいけない部分だけダブルチェックするという方法もあります。
8.時間を空けて再チェックする
一度見直した後でも、時間を置いてから改めて読み返すと、新たなミスが見つかることがあります。
時間を空けずにチェックすると「さっき確認したから大丈夫なはず」といった油断が生じやすくなるため、一晩置いたり、いったん別の作業を挟むなど、頭を切り替えることが重要です。
9.校正ツールを活用する
ここまでご紹介してきたポイントは、いずれも誤字脱字を防ぐうえで効果的ですが、人の目だけで完全にミスをなくすのはやはり難しいものです。そんなときには、校正ツールや誤字脱字チェッカーなどの活用もおすすめです。
これらのツールは誤字脱字に加え、表記ゆれや文法ミスなども検出できるものがあり、より読みやすい文章を作成するために役立ちます。
アナログ(人の目によるチェック)とデジタル(ツールによるチェック)を組み合わせることで、より高い精度で誤字脱字を見つけることができるでしょう。
まとめ
今回は、誤字脱字が起こる原因や、チェック時に押さえておきたいポイントについてご紹介しました。
どんなに内容が素晴らしい文章であっても、誤字脱字が多いと読者に不信感を与えたり、全体の印象を損ねてしまうおそれがあります。
文章作成において誤字脱字は完全には避けられないものですが、今回ご紹介したポイントを意識しながら、丁寧に時間をかけて確認することが重要です。ぜひ今後の文章作成の参考にしてみてください。