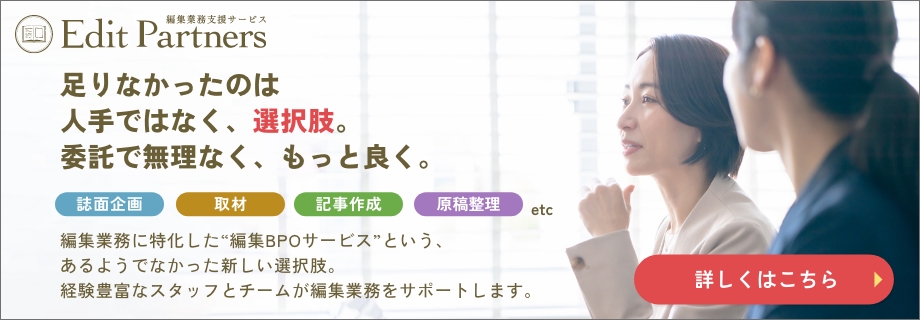2025年4月25日
今さら聞けない校正用語を解説!チェックすべき5つのポイントとは?

目次 ▼
この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。
校正とは?
校正とは、印刷物などの制作過程において、文章やレイアウトにミスがないかを確認し、必要に応じて修正する作業のことです。具体的には、誤字脱字、表記統一、レイアウトや体裁の乱れなどをチェックします。編集やデザインの現場では欠かせない工程で、読みやすく正確な文章を仕上げるために重要なステップです。校正には、文字だけを確認する「文字校正」と、色や印刷の仕上がりも含めて確認する「色校正」があります。
校正には、主に次のような役割があります。
1.原稿が正しくレイアウトされているかを確認する
2.指示した赤字が正しく反映されているかを確認する
3.誤字・脱字・表記ゆれなど、文字の誤りを見つけて修正する基本的には、原稿と初校、初校と再校といった形で照らし合わせ、原稿のとおり配置されているか、修正指示が正しく反映されているかを確認する作業です。
また、誤字・脱字や表記統一、文法上の誤り(「てにをは」など)を正すことも「校正」の重要な役割となります。
引用:校正と校閲の違いとは?ミスを減らすための4つのポイント – 神楽坂編集室
「校正」と混同されやすい言葉に「校閲」があります。
校正は文字の誤りや表記ゆれ、体裁の乱れなどの形式的な誤りを確認し、修正する作業であるのに対し、校閲は事実関係の誤りや矛盾、不適切な表現など、内容の誤りを確認し、修正する作業です。どちらも文章の質を高めるために欠かせない工程ですが、確認するポイントが異なっています。
▼校正と校閲の違いについては、以下の記事でより詳しく解説しています。
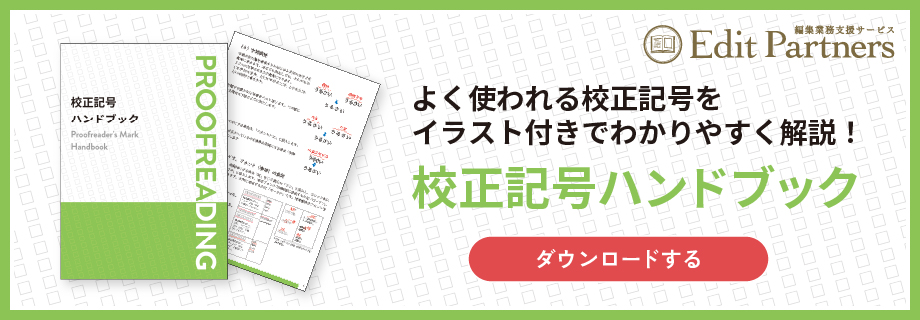
校正でよく使われる基本用語
素読み(すよみ)
原稿と照らし合わせず、校正紙のみをじっくりと読み進めながら確認する校正方法です。校閲でもよく用いられます。
突き合わせ
原稿と校正紙を照らし合わせながら、一字ずつ確認していく校正方法です。チェックした箇所に印をつけたり、マーカーで線を引くことで、精度が高まります。
読み合わせ
校正者が二人一組で行う校正方法です。一人が原稿を読み上げ、もう一人が校正紙を見ながら誤りがないかを確認します。音読することによって、ミスに気が付きやすくなります。
二人一組で行うのが難しい場合は、音声読み上げソフトを活用するのも一つの方法です。以下の記事では、無料で使える音声読み上げソフトを紹介しています。
朱字(あかじ)
赤いペンで書き込まれた修正指示のことを指します。朱書きとも呼ばれます。
校正紙
校正作業のために印刷された試し刷りや、その用紙のことです。 校正刷り、ゲラ、プルーフとも呼ばれます。
入稿
印刷会社や制作会社に、印刷用の原稿やデータを渡すことです。校正の必要がなく、そのまま印刷できるデータを渡すことを「完全データ入稿」と呼びます。
初稿
クライアントが最初に渡す原稿のことです。「初稿」と「初校」は別の意味なので、混同しないよう注意しましょう。
初校
初校は、初稿をもとにデザイン・レイアウトを行った最初の校正用データのことです。初校では、原稿が正しくレイアウトされているか、テキストや素材に誤りがないかなど、全体的なチェックを行います。
初校を確認し、修正指示を書き込んで印刷会社に渡すことを「初校戻し」と言います。
再校
初校戻しの内容を反映させた2回目の校正用データのことです。二校(にこう)とも呼ばれます。再校を確認し、修正指示を書き込んで印刷会社に渡すことを「再校戻し」と言います。
以降は、校正の回数にあわせて「三校」「四校」……と続きます。
念校
校了前の最終確認として行う校正、またはそのデータのことを指します。
内校(うちこう/ないこう)
制作側が行う内部チェックのことです。クライアントへ提出する前に、作業者がセルフチェックを行うことを指します。
校了
校了は「校正終了」の略で、すべての修正が完了し、印刷して問題ないと判断された状態のことです。
責了
責了は「責任校了」の略で、修正が少なくクライアントによる確認が不要と判断された場合に、制作側が責任を持って修正・確認し、校了とすることです。

校正時にチェックしたい5つのポイント
ここからは、校正時にチェックしたいポイントを5つご紹介します。こうした点は原稿作成時に意識するのが理想ですが、レイアウトされた初校を見て初めて気が付くケースも多いです。初校のタイミングで細かくチェックするようにしましょう。
1.誤字・脱字
打ち間違いや変換ミス、文字の抜けなどがないかを丁寧に確認しましょう。人間の脳は、単語の最初と最後の文字が合っていれば中間の文字が多少違っていても無意識に補正して読んでしまう特性があります。思わぬ見落としが起こりやすいため、一文字ずつ入念にチェックすることが大切です。
▼誤字脱字を防ぐ具体的な方法は、以下の記事で解説しています。
2.表記ゆれ
「表記ゆれ」とは、同じ意味の言葉に対して複数の表記が混在していることを指します。例えば、「もの」と「物」、「ホームページ」と「Webサイト」など、語句や言い回しが文中で統一されているかを確認しましょう。あらかじめ社内や媒体ごとの表記ルールをまとめておくのも効果的です。文化庁などが公開している外部の基準を参考にするのもよいでしょう。
▼表記ゆれを防ぐ方法やチェックポイント、参考になるガイドラインなどは、以下の記事で詳しく紹介しています。
3.漢字とひらがなの使い分け
表記ゆれに関連して、漢字とひらがなのバランスや使い分けも重要なチェックポイントです。例えば、「ください」「下さい」といった表記の混在がないかに加え、全体として漢字が多くなりすぎていないかもあわせて確認しましょう。特に、難読漢字や常用外漢字が多く含まれていると、読者にとって読みづらく堅苦しい印象を与えてしまうことがあります。「漢字30%:ひらがな70%」の割合を意識し、バランスよく使い分けましょう。
▼以下の記事では、漢字とひらがなを使い分けるポイントをご紹介しています。
4.段落や改行の位置
原稿の状態とレイアウト後では、段落や改行の見え方が異なることがあります。読者にとって読みにくくなっていないか、意図しない箇所で段落が切れていないか、改行が足りず文章が詰まりすぎていないかなど、全体を一通り読みながら確認しましょう。
5.数字や記号の表記
数字や記号は、ミスや見落としが起こりやすい部分です。桁数や単位の間違いは大きな影響を与える可能性があるため、特に慎重にチェックしましょう。
加えて、全角・半角が統一されているか、「CO₂」「10²」などの上付き・下付き文字が正しく表示されているかも確認します。さらに、原稿で環境依存文字や特殊記号を使用している場合、初校作成時に文字化けが発生する可能性もあるため注意が必要です。
まとめ
今回は、校正でよく使われる基本的な用語と、校正時にチェックすべきポイントについてご紹介しました。
校正は文章の完成度を高め、読者にとってわかりやすく信頼性のある情報を届けるために欠かせない工程です。基本用語や注意点を把握しておくことで、印刷会社とのやりとりがスムーズになり、校正の精度向上にもつながります。ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。
校正記号の種類や使い方については、以下の記事でご紹介しています。